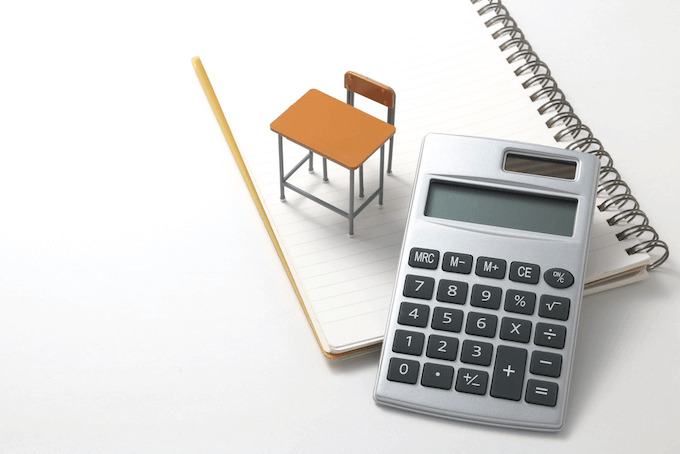イヤでも貯まる!月5000円からの「積立貯蓄」

更新日:2020/10/21
「貯蓄はしたいけど、いきなりまとまったお金を貯蓄に回すのは難しい」というカップルにオススメなのが、毎月少しずつコツコツと積み立てていく「積立貯蓄」。たとえ少額でも、長期間積み立てることで、まとまったお金を貯めることができます。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
意外と貯まる!コツコツ貯蓄

「まずは100万円貯めたい」と思っても、いきなり毎月何万円も貯蓄をするのは難しいという人もいるでしょう。短期間で一気に貯めるのは厳しくても、毎月数千円を貯蓄に回して積み立てれば、時間の効果でまとまったお金を貯めることができます。
例えば毎月5000円を貯めるのであれば、それほど負担は大きくないのではないでしょうか。毎月5000円を積み立てるだけでも、1年間で6万円、10年間で60万円を貯めることができます。共働きの場合、夫婦それぞれが5000円ずつ積み立てれば、さらにこの倍の金額が貯まることに!
少しずつでもお金が貯まっていけば、貯蓄する喜びも感じられます。貯蓄体質になるためにも、まずは少額からでいいので、積立貯蓄をスタートしてみましょう。
会社員なら財形貯蓄を活用しよう

会社員で、会社に制度があればぜひ活用したいのが「財形貯蓄」。財形貯蓄とは、会社から振り込まれる給与から、自分が決めた金額を指定の口座に自動積み立てできる制度です。給与から天引きされるため、無理なく自然に積立貯蓄ができるのがメリットです。
財形貯蓄には3種類があります。
| 一般財形貯蓄 | 使用目的が限定されていない。加入者の年齢制限はなし。積立期間は原則3年以上だが1年経過すると払い戻しも可能。税金の優遇措置はない。 |
| 財形年金貯蓄 | 老後資金の準備に活用できる財形貯蓄。受け取りは60歳以降。満55歳未満が加入可能で、原則5年以上の積立期間が必要。税金の優遇措置がある(貯蓄型は550万円まで、保険型は385万円まで非課税)。 |
| 財形住宅貯蓄 | 住宅の購入・リフォーム資金を準備するための財形貯蓄。満55歳未満が加入可能で、原則5年以上の積立期間が必要。税金の優遇措置がある(貯蓄型・保険型共に550万円まで非課税)。 |
新婚夫婦なら、目的が限定されない一般財形貯蓄か、住宅購入を目的とする財形住宅貯蓄がよいでしょう。一般財形貯蓄は積立期間が3年以上ですが、中途解約が自由にできるというフレキシブルさが魅力。 また、財形住宅貯蓄は積立期間が5年以上で、積立目的は住宅購入・リフォーム費用に限られますが、1年以上継続し残高が50万円以上あれば、残高金額の10倍まで、住宅取得資金の80%まで(最高4000万円まで)の財形持家融資を受けることができます。
財形貯蓄は会社の福利厚生の仕組みなので、この制度がある会社、ない会社があります。自分の勤め先に財形貯蓄制度があるか確認して、あれば活用を検討しましょう。
銀行の自動積み立て定期や貯蓄型保険も活用しよう

メインバンクを活用するなら、自動積み立て定期が便利。設定した額を毎月給与引き落としなどで自動的に積み立てられるため、いつの間にかお金が貯まります。
また、毎月保険料として一定額が引き落とされる貯蓄型の保険を利用するという方法もあります。保険料が毎月自動的に引き落とされるため、銀行口座のように「ついお金を引き出してしまう」ことができないのも、このタイプの保険のメリットの一つです。
貯蓄型の保険として代表的なのが「終身保険」。死亡・高度障害状態になった際に保険金が受け取れるだけでなく、満期時や解約時に満期保険金や解約保険金を受け取れるという貯蓄の機能があります。ただし、貯蓄の分が保険料に上乗せされている仕組みのため、掛け捨て型よりも保険料が割高であるという側面もあります。
将来の子どもの教育費などを貯めるなら、「学資保険(子ども保険)」を活用するという手もあります。
学資保険には貯蓄重視タイプと保障重視タイプがあります。保障重視タイプは契約者(親など)が死亡した際に育英年金がもらえたり、病気やケガによる入院時に入院給付金を受け取れるなど保障が手厚くなっています。保障の手厚さというメリットがある一方で、払い込んだ保険料よりも受け取れる保険金が下回ってしまうケースが多いので、シンプルにお金を貯めるのが目的の場合は、返戻率(払い込んだ保険料に対して受け取れる給付金の率)が100%を上回る貯蓄重視タイプを選ぶとよいでしょう。
このように、お金を貯めるには「自動的にお金が貯まる仕組み」を作ることが大切。一度設定してしまえば、あとは放っておいても貯まるのが積立貯蓄の強みなので、いち早く仕組み作りをするようにしましょう。
できるだけ貯蓄をしたいけれど、生活費を圧迫してしまっては元も子もありません。ゼクシィ保険ショップでは、おふたりだけの家計プラン表を作成してプレゼント。ふたりの収入に合った、無理なく貯められる貯蓄額や家計バランスがわかります。貯蓄型保険や外貨建て保険の取り扱いもあるので、将来のお金が気になる方もお気軽にご相談ください。
※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00356-2009