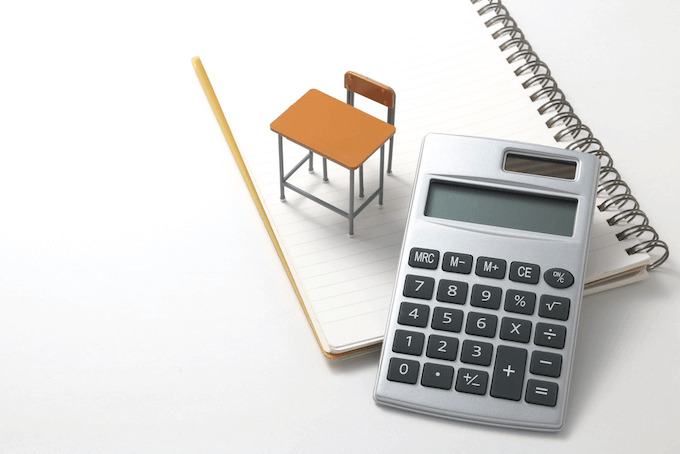「家を買うお金」現金はどれぐらい必要?

更新日:2020/10/22
「いつかは自分の家が持ちたい!」そんな夢を持っているカップルも多いと思います。果たして、家を買うにはどのくらいの貯蓄が必要なのでしょうか? ここでは、家を買うためのお金について考えていきましょう。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
頭金ゼロで買えるが、20%程度を用意しておくのがベター
ひと昔前までは、住宅ローンを組むには頭金を入れなくてはなりませんでした。しかし、近年、銀行間で住宅ローンの獲得競争が過熱した結果として、「頭金ゼロでも買える!」という銀行が増えています。
頭金ゼロで買えるなら、貯蓄がなくてもマイホームを買えるのでは?と考える人もいるかもしれません。しかしこの考えはNG!「頭金が用意できる人」は、貯蓄がしっかりできる人と判断される傾向にあるため、金融機関の審査に通りやすいのです。一方で、貯蓄がゼロの人の場合、返済能力が低いとみなされ、審査に通らない可能性も出てきます。また、もし貯蓄がなく頭金ゼロで買えたとしても、その後のローン負担が重くなることは間違いありません。
さらに、マイホームを購入した後、何らかの理由で売却が必要になったときのことも考えておく必要があります。頭金ゼロで購入したケースでは、売りたくても売れない状況に陥ってしまう可能性が高くなります。マイホームを売却するときに、住宅ローン残高のほうが多い状態だった場合、物件の売却価格と住宅ローン残高との差額を現金で用意しないとスムーズに売却が進まないからです。
マンションなどの物件では、購入した時点でその担保価値が購入した価格から10~20%程度下がるのが一般的です。そのため、頭金ゼロで購入して、途中で売却しようと思っても、住宅ローン残高と物件の担保価値との間に差がある状態が長く続き、売るに売れない状況になります。初めから、ローン残高と物件の担保価値の差額である20%程度を、頭金として入れておけば、担保割れもしにくくなります。
これらの理由からもやはり、物件価格の20%程度の頭金は用意しておきたいところです。
家を買うためには物件価格の30%の現金が必要!?

マイホームを購入する際には、20%程度の頭金分のほかにも現金で用意しておくべきものがあります。
まず、マイホーム購入時には、登記費用や住宅ローンの保証料などの「諸費用」が必要となります。ざっくりとした目安は新築なら物件価格の5~7%程度。中古の場合は、不動産会社への仲介手数料がかかるので、物件価格の10%程度を現金で用意しておく必要があります。4000万円の物件なら、新築で200万円(5%の場合)、中古で400万円ほどは必要になる計算です。
そのほかにも、新居に移る際には引っ越し代も必要になりますから、新築であれば頭金を含めて物件価格の30%程度の現金を用意しておくのが万全です。
物件価格の30%の現金、どうやって用意する?

4000万円の物件を購入しようと思ったとき、2割の頭金に加えて中古マンションなら諸費用が物件価格の10%程度かかりますので合計すると物件価格の30%程度を現金で用意しようとすると、1200万円が必要ということになります。
頭金を含めた現金を増やす方法の一つとして、まずは親や祖父母から贈与という形で援助を受けることが挙げられます。本来、資金を贈与された場合は、たとえ親族からであっても贈与税の対象となり、税金がかかります。しかし、「住宅資金贈与の非課税の特例」など、贈与税を節税できる優遇制度がありますので、資金提供を受ける可能性がある人は、条件やポイントを押さえたうえで利用するとよいでしょう。
2つめの方法は、親から借りること。「贈与」とみなされないよう、親子であっても借用書を作成してから借ります。金利や返済方法を設定し、計画通りに銀行振り込みで返済するようにしましょう。万一、税務署から「贈与では?」と疑われた場合でも、返済実績の記録があれば、正式な借金であることの証拠になります。
最後に3つめとして、自分でお金を貯めること。積み立てられる期間が長ければ長い程、月々積み立てなければならない金額は下がり、無理なく貯蓄ができるようになります。積み立ては少しでも早く始めることがポイントです。マイホームを買いたいと思ったら、すぐに「家を買うお金」に向けた貯蓄をスタートさせましょう。ローン契約日までに貯蓄して頭金を増やし、借入金額を減らすことができます。ボーナスを使わずに貯める、家計を見直して貯めるなどの方法で、少しでも頭金の額が増えるようにしましょう。
ゼクシィ保険ショップでは、「我が家の適正な貯蓄額がわかりません」というお悩みをもつお客さまのためにおふたりだけの家計プラン表を作成してプレゼントしています!現在の世帯収入と支出をお聞きし、今後の住宅購入や妊娠・出産などのライフプランを考慮しながら、毎月どのくらいの貯蓄額がおすすめなのか、グラフで可視化しつつアドバイスしています。
※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00378-2010