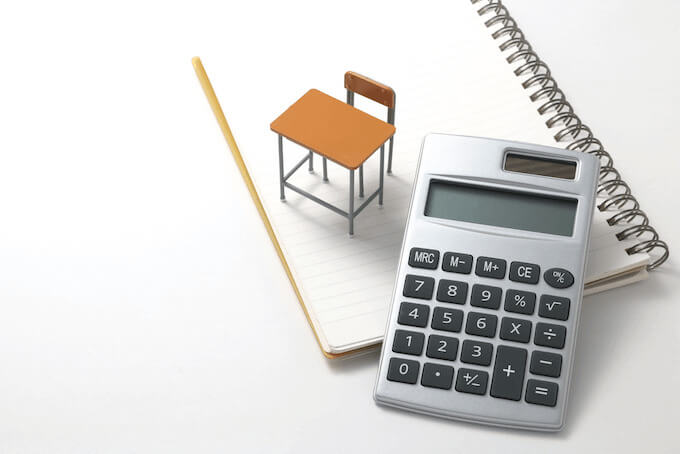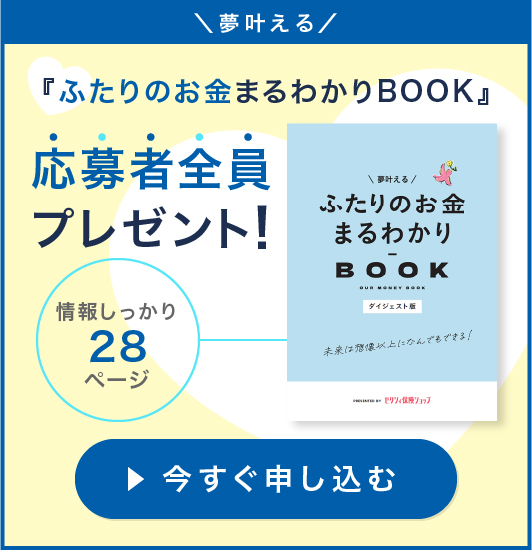50代におすすめする生命保険は?加入率や選び方・見直しのポイントをまとめて解説!

更新日:2024/03/29
自分では元気なつもりでいても、50代になると、知らず知らずのうちに体力や気力は減退し、男女問わず病気やケガのリスクが高まります。そのため、もしものときへの備えは重要であり、その方法の一つとして生命保険があります。50代であれば、大半の人はすでに生命保険に加入済みです。この記事では、50代にとっての生命保険の必要性や加入率、加入している保険の種類、選び方、見直し方などを解説します。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる


生命保険の必要性

ではまず50代にとっての生命保険の必要性について見ていきましょう。
50代が抱えるリスクとは?
50代が抱えるリスクとは何かを考えたときに、まず病気やケガによる入院費がかさむことがあげられます。厚生労働省の「令和2年 患者調査」を基に、男女別に入院の理由として多いものを見てみましょう。
〈男性〉
50〜59歳の入院理由として最も多いのは「精神及び行動の障害」で、以下「循環器系の疾患」「新生物(腫瘍)」となっています。
〈女性〉
50〜54歳の入院理由として最も多いのは「精神及び行動の障害」で、以下「新生物(腫瘍)」「神経系の疾患」となっています。
また、55〜59歳の場合では、「精神及び行動の障害」が最も多く、以下「新生物(腫瘍)」「循環器系の疾病」となっています。
生命保険の必要性は高い
男女共に入院理由の上位に入っているがんを見てみますと、最近ではいろいろな治療法が開発されており、回復に期待が持てるようになりましたが、その分、治療費が高額になるケースが多いです。そのため、高額な治療費への備えとして、生命保険の必要性は高いといえます。
40代~50代になると、病気になるリスクは一気に上昇し、治療費も増えます。
家族が安心して生活できるよう、家計への影響を抑えるためにも、もしものときの生命保険による備えは必要です。
生命保険の加入率は?

多くの人が加入している生命保険ですが、その加入率はどのくらいなのでしょうか?
50代世帯の生命保険加入率は約93%
(公財)生命保険文化センターの「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、すべての年代で、生命保険の世帯加入率が最も高いのは55~59歳(世帯主の年齢)で94.8%でした。
また、50~54歳(世帯主の年齢)では93.0%が生命保険に加入しており、世帯主の年齢が50代の世帯では、約93%が生命保険に加入しているということになります。
その他保険の加入率
医療保障を生命保険で備えている人も少なくありません。
(公財)生命保険文化センターの「令和4年度 生活保障に関する調査」によると、50代で医療保障を生命保険で備えている人の割合は、男性が72.1%、女性が77.2%でした。
また、50代では、がん保険に加入している人も多くなっており、加入率は男性が45.5%、女性が49.2%となっています。
50代の保険料はどのくらい?

(公財)生命保険文化センターの「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、世帯主が50代の世帯の年間払込保険料は、50〜54歳の場合が43万2000円、55〜59歳の場合が43万6000円でした。
生命保険は2タイプに分かれる
生命保険を検討するに当たり、まずは生命保険には、終身型保険と定期型保険の2つのタイプがあることを押さえましょう。
終身型保険
終身型保険とは、保障される期間が一生涯となっている保険です。被保険者(生命保険の対象として保険がかけられている人)が死亡した場合に保険金を受け取ることができます。
また終身型保険は保障だけでなく貯蓄の機能も兼ね備えており、契約の途中で解約すると解約返戻金を受け取ることができます。そのため一般的には貯蓄機能がない定期型保険よりも保険料が高いというデメリットがあります。
定期型保険
定期型保険とは、10年や20年など一定期間内に死亡した場合に保険金を受け取ることができる保険です。いわゆる「掛け捨て型」の保険で保障に特化しており、保険期間が満了しても満期金はありませんし、一般的には解約返戻金もありません。
貯蓄機能がないため保険料が割安で、ノンスモーカー割引や健康体割引など、自分に合った条件を選ぶことができます。保険期間が満了になると保障がなくなるというデメリットがあります。
生命保険は大きく分けて4種
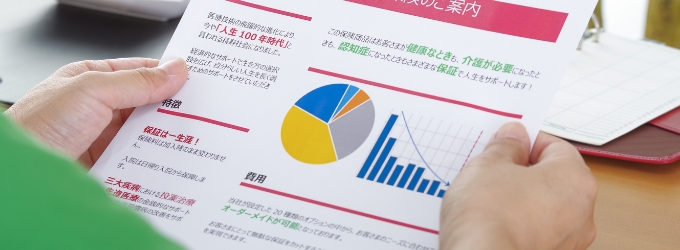
生命保険は大きく分けて医療保険、個人年金保険、がん保険、その他の保険の4種類あります。
医療保険
医療保険とは、病気やケガにより入院したり手術を受けたりしたときに、給付金を受け取ることができる保険です。給付金は入院1日について5000円などの形で決まります。
特約(オプション)を付けることで、三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)などにも備えることができます。
個人年金保険
個人年金保険とは、将来の老後の年金として保険料を積み立てていく保険です。60歳や65歳など契約時に定めた年齢になると、年金の受け取りを開始します。
年金の受取期間は、5年や10年など一定期間の場合もあれば、一生涯にわたって給付される場合もあります。
がん保険
がん保険とは、名称のとおり「腫瘍(がん)」に対する保障に特化した保険です。がんと診断されたら100万円、放射線治療を受けたら月額5万円などというような保障内容があります。
がんは50代にとって、死亡・入院理由の常に上位となっており、備えは重要といえます。
その他の保険
50代が加入しているその他の生命保険としては、終身保険、定期保険、収入保障保険、就業不能保険、養老保険などがあります。
保険にはそれぞれ特徴がありますので、その特徴をよく理解するとともに、保険料負担のことも考慮して、仕事の安定性や収入などを踏まえて検討しましょう。
生命保険の選び方

自分に合った生命保険の選び方は、結婚しているのか独身なのか、結婚していても子どもがいるのかいないのか、また子どもは独立しているのかいないのか、によって変わってきます。
ここではケースごとに選び方のポイントをまとめました。
既婚者の場合
結婚していても、子どもがすでに独立している家庭もあれば、まだ独立していない家庭もあります。また、結婚していても、子どもはいないという夫婦もいます。
このように結婚していても状況は異なっていますので、それぞれのケースに分けて解説します。
子どもが独立している
まずは、結婚していて、すでに子どもが独立しているというケースです。
独立していれば子どもにも一定の収入があるので、大きな死亡保障は必要ないといえます。自分にもしものことがあっても、すでに子どもの生活費や教育費はかからないからです。
ただし、残された家族に迷惑をかけないためにも、自分の葬儀費用や墓地購入費用などは、用意しておきましょう。目安としては300万円ほどの死亡保障があれば安心です。
子どもが独立していない
次に、結婚していて、まだ子どもが独立していないというケースです。
自分にもしものことがあった場合、子どもの生活費や教育費をカバーしなければならないので、十分な死亡保障が必要といえます。子どもの年齢にもよりますが、ある程度のまとまった保障が必要になると考えられます。
子どもがいない
そして、結婚しているものの、子どもがいない夫婦のケースです。
このケースでは、すでに子どもが独立している家庭と同様と考えられるため、高額な死亡保障は不要といえます。ただし、子どもがいないので、自分が死亡した後にパートナーが困らないようにするための最低限の保障は必要と考えられます。
独身の場合
最後に独身のケースです。
独身の場合は、自分の葬儀費用や墓地購入費用などに備える分の保障があれば十分と考えられます。例えば、納骨堂などを利用すれば墓地購入費用は抑えることができるので、必要な保障額を減らすことができます。
最後はどのようにしたいのか、自分自身で決めることが重要になります。
生命保険の見直し方

現在加入している生命保険を見直すに当たり、どのような視点で行えば良いのか、見ていきましょう。
保険料を減らす
まずは保険料の負担を今よりも減らせないかを検討してみましょう。
子どもが独立すると大きな保障がいらなくなるため、死亡保障の保障額を減らすことができます。また、不要な特約を解約することでも、保険料の負担を減らすことができます。
払い済み保険に変える
払い済み保険に変えることを検討するのも見直し方法の一つです。
払済保険とは、以後の保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に、保険期間はそのままで、保障額の少ない保険に変更する方法です。保険料の払い込みを中止するものの、解約するわけではないので、一定の保障が続きます。
定期保険に変える
終身型の保険から、定期型の保険へ変更するだけでも保険料の負担を抑えることができます。
ただし定期型の保険の場合、保障額は同じですが、元々の終身型の保険よりも保険期間が短くなります。
払い済み保険と似ている延長定期保険という見直し方法もあります。延長定期保険とは、以後の保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に、保障額を変えないで、一時払の定期保険に変更する方法です。
生命保険に関するQ&A
生命保険に関するQ&Aをいくつかご紹介します。
最低限、加入しておきたい保険は?
50代が最低限、加入しておきたい保険としては次の通りです。
・医療保険
・がん保険
・個人年金保険
50代になると年齢的に病気にかかるリスクが高まります。また、老後生活資金に備えなければならない時期でもあります。さらには自分の葬儀費用や墓地購入費用などに備えるために終身保険も考えられます。
50代の女性に必要な保険は?
女性の場合は、ライフスタイルの変化によって保険の内容も大きく変わってきます。しかし50代となると、男性と女性の間に大きな差はないと考えられるので、前出の「最低限、加入しておきたい保険は?」に対する答えと同じです。
なお、保険の中には、女性向けのプランもあるため、ぜひ検討していただくことをおすすめします。
独身は保険に加入しなくてもよい?
結論から申し上げますと、独身の人でも保険は必要といえます。病気やケガによる入院費用や手術費用を貯蓄だけで賄えるとは限らないからです。
特に50代は年齢的にも三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)のリスクが高まるため、最低限の保険には加入しておいた方がいいでしょう。
保険未加入でも安心できる貯蓄額は?
1人当たりの生涯にかかる医療費は、平均して2700万円ほどといわれています。年齢が上がれば病気にかかるリスクも高まるので、医療費も高額になってきます。
もしものときに備えて最低限の保険に加入しておくことをおすすめしますが、貯蓄だけで対応すると考えると、3000万円近くはどうしても必要になるでしょう。
状況に応じて最適な保険を選びましょう
50代は病気のリスクが高まること、そして既婚・独身、子どもがいる・いない、子どもが独立している・独立していないなど家庭の状況に応じて、生命保険の選び方や見直し方が異なることに注意しましょう。
保険の選び方に困ったらプロに相談してみるのもおすすめです。
ゼクシィ保険ショップでは、家計・保険・ライフプランニングについて、まとめて相談できます。さらに何度相談しても無料です。保険選びに迷ったら一度相談してみてはいかがでしょうか。
※掲載の情報は2024年3月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。


RT-00575ー2403