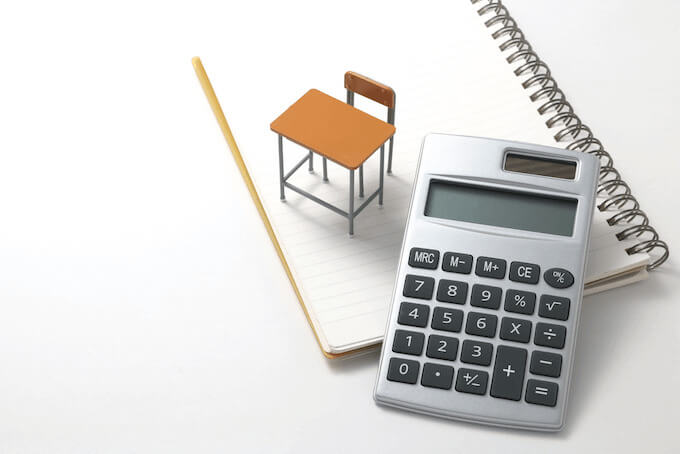保険に入っていないけど、保険は本当に必要?

更新日:2020/10/30
保険に加入した方がいいのか悩みつつも、保険料を支払う必要があることから「本当に必要なのかな?」と足踏みをしている人もいるでしょう。ここでは、万一のときのリスクがどれぐらいあるのかといったデータを基に、保険の必要性について考えていきます。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
病気で死亡するリスクは誰にでもある
保険の中でも、自分に万が一のことがあったときに、配偶者や子どもなど遺族のために加入しておくべきものといわれるのが「死亡保険」です。しかし、自分には万が一のときは来ないかもしれない。あるか分からないことのために、毎月保険料を支払うべきなのか……と考える人もいるでしょう。
では、具体的に病気で死亡するリスクはどれぐらいあるのでしょうか。厚生労働省の「令和元年人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、令和元年の死亡者数は約138万人で、人口1000人に対して11.2の割合で死亡しています。
死因別に見ると、
| 第1位 | 悪性新生物(がん) | 27.3% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 15.0% |
| 第3位 | 老衰 | 8.8% |
となっています。亡くなった人全体のおよそ3.7人に1人が、悪性新生物が原因で亡くなっています。
データを見ると、悪性新生物(がん)、心疾患(急性心筋梗塞)、脳卒中の、いわゆる「三大疾病」で亡くなる率が高いことが分かります。
このデータは全年齢を対象にしているため、必ずしもあなたの年齢でなるとは限りませんが、とはいえ病気で亡くなるリスクは誰にでもあり、「まさかの事態」はいつ起こってもおかしくないと考えるべきでしょう。
高齢になるほど病気のリスクが大きくなる
亡くなるまでいかずとも、病気やけがで入院・手術をするリスクもあります。貯蓄が十分にあれば別ですが、貯蓄に不安がある場合は、入院や手術での出費に対する備えとして、「医療保険」を検討しておきたいものです。
特に、高齢になると病気やけがのリスクが格段に上がります。若いときはよくても、年を取ってから医療費が賄えなくなる可能性もあります。もし死亡保険に加入していても、亡くなるか特定の高度障害状態にならなければ保険金は受け取れません。病気やけがのリスクに備えたければ、医療保険に加入したり、死亡保険に医療保障の特約を付加するといった対応をする必要があります。
なお、ご紹介したデータのとおり、病気の中でも三大疾病のリスクは特に高くなっています。
親族にがん罹患(りかん)者が多いなど、がんへのリスクに特化した保障が欲しければ「がん保険」を検討したり、三大疾病に手厚い「三大疾病保障保険」なども選択肢になります。
保険は経済的な不安を軽減できる
保険の種類はここで紹介した以外にもさまざまです。ただ、種類にかかわらず、基本的に保険というのは公的医療保障でカバーできない部分を補填(ほてん)したり、貯蓄ではとても足りないというお金の不安を軽減してくれたりするものです。
例えば死亡保険。まだ子どもが小さく、自分が家族の経済を支えているという人は、死亡保険に加入しておけば万が一のときにまとまった保険金を受け取れて安心です。仮に死亡保険金3000万円の保険に加入したとします。貯蓄を3000万円準備するのはかなり大変ですが、死亡保険に加入していることで、万一の時にはそのお金を遺族が受け取れ、生活を守ることができるのです。
また、医療保険も同様です。若いときは入院期間や治療期間が短くて済むかもしれませんが、高齢になればそうもいきません。もしも年金暮らしで家計に余裕がなければ、医療費を捻出するのに苦労することが予想されます。しかし、医療保険に加入していれば、給付金で費用を賄うことができます。ちなみに医療保険は、加入年齢が上がるごとに保険料が上がるので、高齢になってからとはいわず、若いうちに検討するのも一つの手です。
保険への加入を迷っている人は、世帯の貯蓄を確認し、もしものことが起きたときに生活がどうなるかを考えましょう。その上で、死亡保険、医療保険、その他の保険にかかわらず、自分にはどんな保障が必要なのか考慮して検討するとよいでしょう。
※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00394-2010