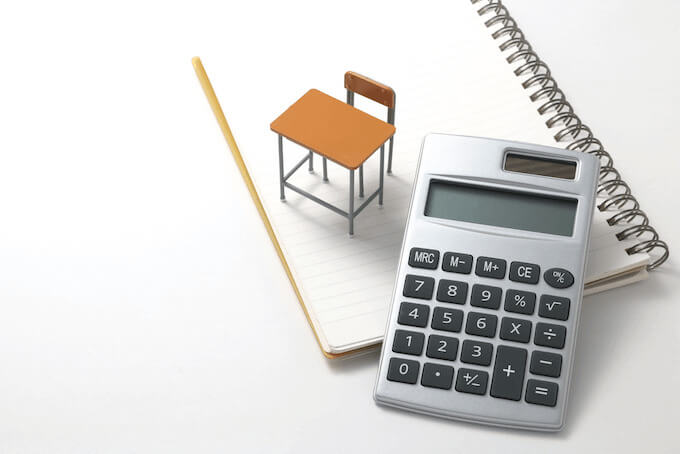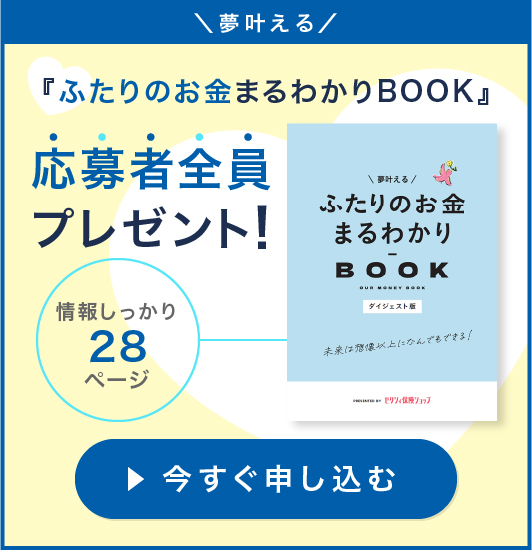生命保険の受取人を変更するには?手順や注意点・税金も解説

更新日:2024/11/28
生命保険(死亡保険)の受取人は保険契約の時に指定します。保険事故が発生する前であれば受取人の変更はできるため、結婚・離婚時など必要に応じて受取人を変更しましょう。本記事では、生命保険の受取人になれる人の条件から変更時の手続きや注意点、保険金受取時の税金まで詳しく解説します。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる


生命保険の受取人とは

生命保険の受取人とは、保険事故が発生した際に保険金や給付金を受け取る人のことです。生命保険に加入する時、契約者(保険料負担者)が被保険者と受取人を指定します。
<生命保険の契約形態>
・生命保険の受取人:対象の生命保険契約の保険金・給付金を受け取る人
・被保険者:保険の対象になる人。被保険者のけがや病気、死亡といった保険事故によって保険金・給付金が発生する
・契約者:保険会社と契約し、保険料を支払う人
生命保険の受取人になれる人
医療保険の給付金は、原則として被保険者が受取人になります。しかし生命保険(死亡保険)は被保険者の死亡によって保険金が出るため、受取人になれるのは被保険者とは別の人です。
死亡保険には被保険者の遺族の生活を保障する役割があります。そのため、一般的に受取人に指定できるのは配偶者または2親等以内の血族です。
<保険金受取人に指定できる人>
・被保険者の配偶者(夫または妻)
・子ども
・孫
・兄弟姉妹
・父母
・祖父母
第三者は受取人になれない?
近年、家族の形は多様化しています。事実婚や内縁関係、または同性のパートナーがいる場合もあるでしょう。保険会社によっては、こうした新しい形の家族も受取人に指定できることがあります。万が一の際、守りたい家族を受取人に指定できるかどうかは重要な問題のため、契約の際は事前に受取人の範囲を確認しておきましょう。
受取人は複数指定できる
生命保険の受取人は複数人を指定できる場合があります。この場合、死亡保険金を請求する際の手続きは保険会社によって異なるため注意が必要です。例えば、複数の受取人それぞれの口座に保険金を振り込んでくれる会社もあれば、代表者1人への振り込みにしか対応していない会社もあります。
受取人を複数人指定したい人は、保険金請求時の対応についてもよく確認しておくといいでしょう。
死亡保険金の受取人はいつでも変更できる?
生命保険(死亡保険)の契約者は、死亡や所定の高度障害状態といった保険事故が発生する前であれば、いつでも保険金受取人を変更できます。ただし、受取人の変更には被保険者の同意が必要です。被保険者に黙って受取人の変更手続きを進めることはできません。
生命保険の受取人を変更する手順

受取人の変更手続きの流れは保険会社や商品によって異なりますが、ここでは一般的な手順をご紹介します。
1、受取人を変更したいと伝える
保険証券を手元に用意し、生命保険会社の担当者またはコールセンターに連絡します。保険金受取人を変更したい旨を伝えて、必要な書類を請求してください。保険会社や商品によっては、インターネット上で手続きできる場合もあります。
2、書類を提出する
受取人変更に必要な手続き書類一式が送られてきたら、必要事項を漏れなく記入し、他の必要書類と併せて提出します。書類に漏れや間違いなど不備があると手続きに時間がかかるため、間違いのないよう気を付けてください。
3、手続きが完了する
受取人変更に関する書類一式を保険会社が確認し、不備がなければ変更手続きは完了です。
死亡保険金の税金
死亡保険金の受け取りには税金がかかります。下記の通り、契約者と被保険者、保険金受取人の関係によってかかる税金が異なるため注意しましょう。
<契約形態によって死亡保険金にかかる税金の違い>

参考:国税庁「№1750 死亡保険金を受け取ったとき」
次から、それぞれの税金について解説します。
相続税
契約者と被保険者が同一で、保険金受取人が法定相続人の契約は相続税の対象になりますが、「500万円×法定相続人の人数」の非課税限度額までであれば、相続税がかかることはありません。
ただし、相続税の非課税枠が適用されるのは法定相続人が受け取る場合です。相続放棄した人や相続権を失った人も含む法定相続人以外の人が受け取ると、非課税枠の適用はありません。
所得税・住民税
契約者と保険金受取人が同一で、被保険者が異なる契約は所得税および住民税の対象です。
死亡保険金を一時金で受け取る場合は「一時所得」の、年金形式で受け取る場合は「雑所得(公的年金以外の雑所得)」の対象になります。それぞれの課税対象額は以下の通りです。
・一時所得:死亡保険金額から特別控除額50万円を差し引いた金額をさらに2分の1にした金額が課税対象
・雑所得:その年中に受け取った年金額からその金額に対応する払込保険料を差し引いた金額が課税対象
受け取り方によって税金の計算方法が異なること、所得税だけではなく住民税の課税対象になる点に気を付けてください。
贈与税
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ違う場合は贈与税の対象です。
贈与税には相続税のような非課税枠はありませんが、基礎控除額110万円を差し引くことができます。また、18歳以上の子や孫が保険金を受け取る場合は特例贈与財産用の税率(特例税率)を適用し、それ以外の人への贈与は一般税率を用いて計算します。
生命保険の受取人に関するポイント

次に、生命保険(死亡保険)の受取人を検討する際に大事なポイントを解説します。
結婚したら受取人の変更を検討する
結婚は、保障内容の見直しや受取人の変更に適したタイミングです。独身時に加入した保険は、父親・母親のどちらかが受取人になっているケースが多くあります。結婚後は配偶者も受取人に指定できるため、必要に応じて変更手続きをしてください。
受取人がわからない場合は問い合わせる
現在の受取人がわからない場合は保険会社の担当者またはコールセンターへの問い合わせや、インターネットの専用マイページにログインすることで確認できます。
保険金受取人は生命保険証券に記載されていますが、最近は紙の生命保険証券を発行せず、PDF形式の電子保険証券を発行している保険会社もあります。保険証券を紛失したり、どこにあるかわからなかったりする場合も、必ず問い合わせをしましょう。
子どもは何歳でも受取人にできる
原則として、保険金受取人に年齢制限はありません。そのため、親を対象にした生命保険の受取人を生まれてすぐの子どもにすることも可能です。
親が契約者・被保険者となる生命保険の受取人を子どもにすれば、相続税の非課税枠を適用できるため相続税対策になります。しかし、死亡保険金受け取りの際に受取人が未成年だと、親権者または未成年後見人が手続きすることになります。未成年の子どもを受取人にする時は、スムーズな手続きの方法やトラブル対策も考えておきましょう。
離婚する場合は早めに手続きする
配偶者が保険金受取人になっている契約がある場合は、離婚前に変更手続きを済ませておきましょう。生命保険金は受取人固有の財産であるため、離婚しても保険金を受け取る権利はなくなりません。
離婚後に保険事故が発生すると、元配偶者でも保険金を請求できることになります。こうしたトラブルを防ぐためにも、離婚が決まったら保険関連の手続きは早めにしておきましょう。
受取人が亡くなった場合は新しい受取人に変更する
通常、保険事故発生時に保険金受取人が亡くなっている場合は、「死亡した受取人の法定相続人」が新たな受取人となります。
ただし、かんぽ生命については独自の遺族制度を設けているため、「受取人の遺族」が新たな受取人となります(※)。どちらにしても、受取人が無指定状態だと手続きに時間がかかるため、受取人が亡くなった場合はすぐ変更手続きを済ませてください。
※出典:かんぽ生命 遺族制度
ライフステージに合わせて保険金受取人も見直しを

生命保険(死亡保険)で万が一のことが発生した時、大切な保障を受け取るのはあらかじめ指定された保険金受取人です。
保険金受取人を誰に指定するかによって、保険金にかかる税金の種類も変わってきます。受け取った後のことも考えた上で、適切な契約形態を検討してください。また、結婚や離婚など、ライフステージの移行に合わせて保障内容や受取人は適宜見直す必要があります。ファイナンシャル・プランナーなど保険の専門家に相談した上で、保険金受取人を設定しましょう。
ゼクシィ保険ショップでも、保険金受取人や保障内容の見直しについての相談ができます。「税金がお得になる契約形態にするにはどうすればいい?」「結婚したので、受取人変更と併せて保障内容も見直したい」などのご相談があれば、無料相談を利用してみてはいかがでしょうか?
※掲載の情報は2024年10月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。


RT-00961-2410