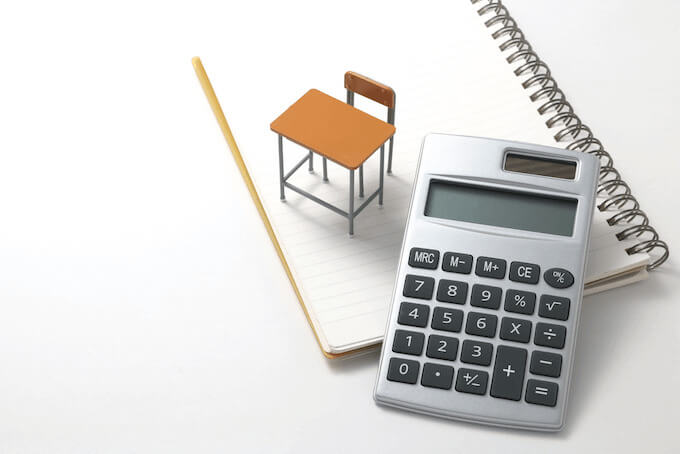住宅ローンを借りたら生命保険の見直しは必要?団信の役割や選ぶ際のポイントも解説!

更新日:2024/11/28
基本的に、民間の住宅ローン契約時には団信への加入が必要となり、保障の重複を避けるため、団信加入時には既契約の生命保険を見直すことが大切です。団信(団体信用生命保険)とは、住宅ローン契約者に万が一のことがあった時、住宅ローン残債をゼロにして遺族の負担を軽減する保険制度。本記事では、団信の仕組みや選び方から団信加入時の保険の見直し方法まで詳しく解説します。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
住宅ローンを組む時は生命保険の見直しも重要

通常、住宅ローンを組む時は金融機関から団信への加入を求められます。団信に加入していれば、住宅ローン契約者が死亡したり、所定の高度障害状態になっても、その時点の住宅ローン残債はすべて保険会社が保障してくれます。
団信に加入する際は加入中の生命保険を見直し、保障の重複がないようにしましょう。団信の加入時、主に見直し対象となる生命保険は以下の通りです。
・死亡保険:死亡時の遺族の生活費を保障する
・医療保険(がん保険を含む):病気やけがによる治療費や収入減少を保障する
・個人年金保険:老後の生活費を保障する
次より、一つずつ詳しく解説します。
死亡保険
被保険者が死亡、または所定の高度障害状態になった時に死亡保険金が支払われます。団信と保障内容が似ているため、住宅ローン契約時に死亡保険の保障額を見直す人は多いでしょう。
見直す際は、死亡保険を減らしすぎないよう気を付けてください。団信は住宅ローンと一体になっているため終身保障ではなく、ローン完済によって保障が消滅します。また、団信は保険金額が直接住宅ローン残債に充当されるため、死亡保険のようにまとまった保険金は受け取れません。
死亡保険は相続税対策にもなるため、保障額を減らしすぎないようにしましょう。
医療保険
被保険者が病気やけがで入院・手術をした時に、給付金が支払われる保険です。働き盛りでも健康リスクはあり、一定期間働けなくなれば住宅ローン返済にも影響があります。
公的医療保険制度だけですべての保障をカバーできるわけではないため、住宅ローン契約時には医療保険やがん保険の保障も検討しましょう。最近は、疾病特約やがん特約を付加できる団信もあります。併せて検討してみてください。
個人年金保険
55歳や60歳など、あらかじめ設定した年齢になると年金または一時金としてまとまった保険金額を受け取れる年金保険です。さまざまな種類があり、中には一生涯の年金保障を得られる商品もあります。
定年後もローン返済が続く場合には、個人年金保険の保険金をローン返済に充当することも可能です。団信とは別で個人年金保険を持っておくと、老後も安心できるのではないでしょうか。
生命保険を見直す理由

住宅ローン契約時に生命保険を見直す主な理由は以下の2点です。
保障内容が重複する
団信は住宅ローン契約者の死亡・所定の高度障害状態を保障する保険で、別途がん特約や3大疾病特約を付加することも可能です。
団信と民間の生命保険は内容が似ているため、一部保障が重複してしまうことがあります。住宅ローン契約時に生命保険を見直すことで、それぞれの備えを最適化することができます。
必要以上に保険料を支払うことになる
団信は保障額が保険事故発生時の住宅ローン残債のため、保障額が大きいことが特徴です。既存の生命保険の内容によっては、必要以上の保障に加入することになり、本来不要な保険料を支払うことになってしまいます。
保障と保険料の無駄をなくすためにも、団信契約時には必ず生命保険を見直しましょう。特に死亡保険は一般団信と保障が似ているため、住宅ローン契約期間中は保障額を減額するなどの対応が必要です。減額の際は、住宅ローン完済後(団信の保障が消滅した後)の死亡保障まで減らしすぎないように注意してください。
団体信用生命保険(団信)とは

住宅ローン契約者が死亡した場合、その時点で残っている住宅ローンの返済分をすべて保障する保険制度が団信です。
団信の保障は住宅ローン残債と連動しているため、一般の死亡保険のようにまとまった保険金額が手に入るわけではありません。契約者死亡後の生活費や教育費といった支出は、貯蓄や生命保険で準備する必要があります。
ここでは、団信の基本的な仕組みや保障の範囲、保険料の支払い方法など、団信の概要を詳しく解説します。
保障される範囲
基本的に、民間住宅ローンに付帯している団信は「一般団信」です。一般団信では、契約者が死亡、または所定の高度障害状態になった時の住宅ローン残債を保障します。保険事由が発生した際の保険金額は住宅ローンの残債と連動しているため、返済進捗(しんちょく)に応じて保障額は減少していきます。
「一般団信」のほか、がん(悪性新生物)と診断確定を受けると残債がなくなる「がん団信」など、特約付きの団信もあります。特約付き団信の取り扱いや保障内容は金融機関によって違うため、詳細は金融機関に確認してください。
保険料の支払い方
一般団信の保険料は金融機関が負担するため、住宅ローン契約者が別途支払う必要はありません。
ただし、がん団信や3大疾病団信など、特約付き団信は保険料が必要になるのが一般的です。保険料の支払いは「住宅ローン金利上乗せ方式」または「別途保険料支払い方式」があり、主流は金利上乗せ方式です。上乗せ金利は金融機関や付帯する団信特約によって変わりますが、年0.1%〜0.3%程度が相場となっています。
団信に加入するための条件

団信に加入する条件は以下の2つです。それぞれ詳細を解説しましょう。
住宅ローンをこれから申し込む
団信は、住宅ローン契約時にのみ加入できる保険です。
住宅ローン契約後に特約を追加したり、保障内容を変更したりすることはできません。また、住宅ローンを完済すると保障は消滅します。住宅ローン契約時には、特約付き団信も併せて慎重に団信を検討することが重要です。
健康である
一般団信および特約付き団信には所定の健康告知が必要です。告知した健康内容を団信の保険会社が審査した上で、団信への加入が決まります。通常、民間の金融機関では住宅ローンの利用時に一般団信の加入を求めているため、一般団信に加入できない人は、住宅ローン契約が難しくなります。
特に気を付けたいのは、直近5年以内のがんや重病の既往症がある場合や、所定の身体障害がある場合です。また、健康診断で指摘を受けた後、再検査をしていない場合も注意が必要です。加入したいからといって虚偽の告知をすれば、万が一の時に団信保障を受けられないというリスクがあります。
不安のある人は、金融機関の担当や団信の保険会社に健康状態の要件や告知の方法を確認してみましょう。
団信の種類と保障内容

ここでは、団信の種類を「一般団信」「ワイド団信」「疾病保障付き団信」の3つに分けて解説します。
一般団信
一般団信とは、住宅ローン契約時に加入が求められる必須の団信です。契約者が死亡または所定の高度障害状態になると、その時点の住宅ローン残債が保険会社より金融機関に支払われます。基本的に、契約者の保険料負担はありません。
ワイド団信
ワイド団信とは、健康上の理由で一般団信に加入できない人向けの引き受け基準緩和型団信です。健康告知の項目が簡素化されており、軽度な高血圧や糖尿病など、持病がある人でも加入しやすくなっています。ただし、病気の状態によって加入可否は異なるため、加入を約束するものではありません。
ワイド団信では引き受け基準が緩和されている分、加入には上乗せ金利が必要です。一般的には、年0.2~0.3%程度の金利が上乗せされます。
疾病保障付き団信
一般団信にがんや3大疾病などの疾病保障を追加した団信で、特約付き団信ともいわれています。がん団信から3大疾病保障付き団信、8大疾病保障付き団信、11疾病保障付き団信、全疾病保障付き団信まで、種類はさまざまです。
疾病保障付き団信の上乗せ金利は金融機関によって異なります。一部の金融機関では、がん団信を上乗せ金利なしで付帯していることもあります。
団信を選ぶ時の確認ポイント

団信を選ぶ時は、以下3つの確認ポイントに留意し、ご自身に合うものを見つけてください。
保障内容
団信には、死亡や高度障害状態以外にも、さまざまな疾病に対して保障がされる特約付き団信があります。
どこまで特約で備えるのか、団信ではなく生命保険で対応するのかどうかを、よく検討してください。団信は万能ではなく、すべてをカバーできるものではありません。団信と併せて、民間の生命保険や貯蓄、健康維持も考慮することが大切です。
保険金が支払われやすいかどうか
団信は保障を提供する保険会社によって、保障内容や保険金の支払い条件が異なります。
一般団信の死亡保障は各社で違いがありませんが、病気や「長期就労不能状態(働けない状態が続いていること)」の支払い条件は団信によって違うことがあります。
病気や就労不能を条件とする団信に加入する際は、パンフレットなどで支払い条件をよく確認しましょう。
金利が上乗せされるかどうか
一般団信以外の団信特約を付帯すると、金融機関によっては上乗せ金利が必要です。
上乗せ金利は0.1%~0.3%が相場です。例えば、3000万円の住宅ローンにおいて、金利年0.45%に0.2%金利を上乗せすると、総返済額は170万円程度増加します。
団信特約の金利上乗せや保険料の条件は金融機関によって違うため、詳細を確認した上で比較検討することが重要です。
自分だけで団信を選ぶと判断が難しいこともあります。その場合は、住宅ローンの内容だけではなく、団信の内容についても金融機関の担当者に相談して判断するようにしましょう。
住宅ローン契約時の注意点

団信があるとはいえ、団信の保障だけで長期にわたる住宅ローン契約をカバーできるとは言えません。ここでは、住宅ローン契約時の注意点を3つ解説します。
団信だけでは不十分
一般団信で保障されるのは、契約者の死亡および所定の高度障害状態です。
病気やけがで短期的な入院をした場合、会社員であれば有給休暇や傷病手当金で対応できますが、フリーランスは自営業であればそのような所得保障はありません。会社員でも、治療が長引けば有給休暇や傷病手当金だけでは不足することがあります。
一般団信に加入したら十分というわけではないので、民間の保険と併せて、病気やけが、働けないときの保障を慎重に検討しましょう。
団信ではカバーできないリスクがある
団信では一般団信のほか、特約によってがんや3大疾病といった病気にも対応できます。
ただし、各特約には保険金支払いの条件があり、病気の状態によっては支払い対象外となる可能性もあります。カバーできないリスクがあることを理解した上で、貯蓄や健康維持で備える姿勢も重要です。
完済すると保障期間も終了する
団信の保障は住宅ローンと連動しているため、住宅ローンを完済すれば保障期間は終了します。
多くの場合、民間の住宅ローンの完済時年齢は80歳未満。80歳以降は住宅ローンも団信保障もなくなるという人が多いため、80歳以降も長生きした場合のリスクを考えていかなければなりません。人生100年時代、90歳、100歳まで生きる可能性は十分あります。年齢が上がると民間保険の加入条件は厳しくなるため、早めの保険見直しが重要です。
一般団信に加入できない時は

一般団信に加入できない場合、民間住宅ローンの契約者になることは難しくなります。
過去の病歴や健康状態で一般団信への加入が難しい場合は、引き受け基準が緩和されたワイド団信を検討するか、団信加入が任意のフラット35を検討しましょう。
ワイド団信で団信に加入する場合は、上乗せ金利が年0.2%~0.3%必要です。フラット35は民間の住宅ローンと違い、団信に加入しなくても住宅ローンを契約できます。団信に加入しない場合は、通常のフラット35から金利を0.2%差し引いて契約します。
また、住宅ローン契約者を収入のある配偶者に変更する方法もあります。配偶者に一定の所得があり、団信に加入できる健康状態であれば、有効な方法として検討できるでしょう。
保険の見直しに迷ったらプロに相談を
住宅ローン契約で団信に加入する際は、併せて既存の生命保険も見直しましょう。生命保険と団信は似ている保障もありますが、基本的な仕組みは違うため別々に保障を持つことが重要です。団信の種類や特約、金利上乗せなどを考慮した上で、自身のニーズに合った備えをすることが大切です。
住宅ローンの契約は長期にわたるため、無理のない返済プランを組むこと、団信や既存保険でのリスク対策が不可欠です。ゼクシィ保険ショップでは、住宅ローンの返済プランやリスク対策を踏まえた保険の見直しについても相談可能です。「住宅ローンを契約することになり、保険の見直しや団信の選び方で悩んでいる」という人は、お気軽に相談してみてはいかがでしょうか?
※掲載の情報は2024年10月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00962-2410