貯蓄型保険で貯蓄できる?掛け捨て型との違いや貯蓄の方法を解説

更新日:2022/5/13
保障機能に加えて貯蓄機能も備えた貯蓄型の保険。貯蓄型保険は、貯蓄が苦手という人でも貯蓄できるメリットがあります。この記事では、貯蓄型保険の仕組みから、貯蓄型と掛け捨て型の違い、さらに貯蓄型保険以外の貯蓄に役立つ方法について解説していきます。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
保険は大きく分けて「貯蓄型」と「掛け捨て型」がある
「もしものとき」に備える保険には、「貯蓄型」と「掛け捨て型」の2つのタイプがあります。まずはそれぞれの特徴について見ていきましょう。
「貯蓄型」保険とは
貯蓄型保険とは、名前の通り、貯蓄性を備えたタイプの保険です。死亡や高度障害など万が一のことがあった場合に死亡保険金が受け取れるのに加えて、解約時や満期時に「解約払戻金」や「満期保険金」としてお金が戻ってくるという仕組みです。
「掛け捨て型」保険とは
掛け捨て型保険は、万が一のための備えに機能を絞った保険。契約期間中に万が一のことが起こった場合には、保険金が受け取れますが、何も起こらなければ、支払った保険料は戻ってこないか、解約返戻金があっても少ないというタイプです。
主な「貯蓄型」保険 4種類
主に貯蓄型に分類される保険には、「終身保険」「学資保険」「養老保険」「個人年金保険」の4種類があります。
終身保険
終身保険は、万が一に備える保険。被保険者が死亡したときに、「死亡保険金」が支払われます。また、生命保険会社によっては高度障害になった場合に高度障害保険金が支払われる場合もあります。保障が一生涯続く保険ですが、途中で解約することも可能。その場合、払い込みの期間等に応じて「解約払戻金」が戻ってきます。
学資保険
学資保険は、子どもの教育にかかる費用を確保するための保険です。大学入学に備え18歳までなど、子どもの年齢に合わせ契約期間を設定し、そのタイミングで保険金を受け取るという仕組みです。さらに、契約者が亡くなった場合は保険料が免除され、被保険者に給付金が支払われます。
養老保険
養老保険は、満期まで生存していた場合は満期保険金受取人に満期保険金が支払われる保険。さらに、契約内容にもよりますが、加入者が保険期間中に亡くなった場合や高度障害になった場合に、死亡保険金受取人に同額の死亡保険金が支払われます。そのため「生死混合保険」とも呼ばれます。
個人年金保険
個人年金保険は、老後のための資金を準備できる保険。国民年金や厚生年金などの公的年金で不足する部分を補う目的で加入するのが基本です。契約時に決めた年齢から毎年一定額の年金が受け取れる仕組みです。年金開始前に亡くなった場合、それまでに払い込んだ保険料に応じた保険金が受け取れます。
主な「掛け捨て型」保険4種類
掛け捨て型保険にも、「定期保険」「収入保障保険」「医療保険」「がん保険」の4つがあります。
定期保険
定期保険は、期限付きで「万が一」に備える保険。保険期間は、「10年」「15年」などの年数や、「60歳まで」「70歳まで」などの年齢によって定めます。基本的に掛け捨て型で、その分保険料が割安である点や、期間が定まっているため見直しが利きやすい点などが特徴です。
収入保障保険
収入保障保険は、期限付きで家族の生活費に備える保険。契約期間中に被保険者が死亡や高度障害状態になった場合に、保険期間満了時まで、家族は毎月もしくは毎年保険金を受け取るという仕組みです。商品によっては、保険金の一部、または全額をまとめて受け取ることも可能です。
医療保険
医療保険は、病気やけがなどで入院や手術をした場合に、その費用が保障される保険です。基本的に医療保険の主契約は、入院すると受け取れる「入院給付金」と、手術を受けたときに受け取れる「手術給付金」となっています。最近では、入院前後の通院に対する「通院給付金」を受け取れるプランも増えてきています。
がん保険
がん保険は、医療保険のうちがんの保障に的を絞った保険。がんと診断され、通院・入院・手術などの治療を受けた場合に保険金が受け取れます。がん保険の給付金には、「診断給付金」、「入院給付金」、「手術治療給付金」、「通院給付金」、「放射線治療給付金」などがあります。
貯蓄型保険のメリット・デメリット
貯蓄型保険にはメリット・デメリットがあります。メリットだけでなく、デメリットもきちんと理解しておきましょう。
貯蓄型保険のメリット
・「もしものとき」に備えながら「貯蓄」もできる
すでに述べたように、貯蓄型保険では万一のときに備えながら貯蓄することができます。保険料を払うことで、自動的に積み立てられ、将来の資金にできるというのが貯蓄型保険の一番のメリットです。
・契約者貸付がある
解約返戻金のある保険商品の多くでは、「契約者貸付」が使えます。これは、解約返戻金を担保にお金が借りられる制度。解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に保険会社が立て替え、契約を継続させてくれるという仕組みで、急にお金が必要になったときに保険を解約しなくてもお金が用意できるのがメリットです。利息は付くものの、一般的なカードローンなどよりは低いのも利点です。
貯蓄型保険のデメリット
・支払う保険料が高い
まず貯蓄型保険のデメリットとして挙げられるのは、積み立て分が含まれるため同じ保障の掛け捨て型に比べて保険料が高いという点。そのため、高額な保障を準備するには保険料が高額となります。
・インフレのリスクがある
また、インフレリスクがある点も貯蓄型保険のデメリットです。将来的に受け取れる金額が決まっている固定金利タイプの貯蓄型保険の場合、インフレが起きたときに資産価値が目減りしてしまう可能性があります。
掛け捨て型保険のメリット・デメリット
掛け捨て型に関してもメリット・デメリットがあります。こちらも併せて押さえておきましょう。
掛け捨て型保険のメリット
・保険料が安い
掛け捨て型の最大のメリットは保険料が安いということ。解約返戻金などがないため、同じ保障の貯蓄型に比べて保険料は割安になります。
・保障内容を充実させやすい
先述の通り、貯蓄型だと保険料が高額になります。その点、掛け捨て型の場合、同じ保険料でも貯蓄型に比べ保障内容を手厚くできるというのもメリットです。
掛け捨て型保険のデメリット
・「もしものとき」がなければお金が受け取れない
掛け捨て型には解約返戻金や満期保険金などがないため、貯蓄型とは異なり、万一のことがなかった場合にはお金を受け取れません。何もなければ、「ただ保険料を払っただけで損」と感じる人にとってはこの点はデメリットとなります。
・基本的に保障期間が定められている
掛け捨て型では基本的に保障期間が年数や年齢によって定められています。期間終了後に、保険契約を更新することも可能ですが、更新する際には保険料が高くなります。また、年齢によっては更新できない場合もあります。
「貯蓄型」と「掛け捨て型」どちらが向いている?
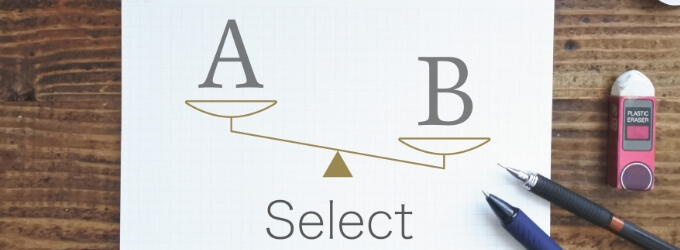
貯蓄型と掛け捨て型それぞれの特徴があり、どちらが向いているかは人によって異なります。両者の特徴を踏まえた上で自分がどちらに向いているかを判断しましょう。
「貯蓄型」保険が向いている人
貯蓄型で払い込んだ保険料はすぐに引き出すことができません。そのため、自分で計画的に貯蓄するのが苦手な人や、お金が貯まるとつい使ってしまう人には貯蓄型はうってつけです。また、子どもの学費や老後の資金など、何らかの目的に合わせて貯蓄しつつ、万一のための保障も欲しいという人にも適していると言えます。
「掛け捨て型」保険が向いている人
掛け捨て型のメリットは割安な保険料で万一の際に備えることができるという点です。そのため、月々の保険料の負担を抑えながら、ライフステージに合わせて適切な保障を確保したいという場合は掛け捨て型を選択するとよいでしょう。また、貯蓄などで資産形成は自分でできるという人は、掛け捨て型の方が向いていると言えます。
貯蓄型保険以外でお金を貯める方法もある

貯蓄型保険は毎月支払う保険料が決まっているので、貯蓄が苦手という人がお金を貯める方法としておすすめです。また保険の他にも、「貯蓄」が苦手な人も取り組みやすい方法があります。以下ではその代表的なものを簡単に紹介します。
つみたてNISA
・長期・積み立て・分散投資を行うための非課税制度
・月1000円など少額から始められる
・年間40万円が上限
・最長20年、利益が非課税
・厳選された商品のみがラインアップされているため投資初心者でも始めやすい
・比較的リスクは低いが元本割れの可能性もある
iDeCo(イデコ)
・老後資金を準備するための年金制度
・自分が拠出した掛け金を自分で運用し、資産形成をする
・毎月支払う「掛け金」が全額所得控除になる
・運用期間中の利益も非課税
・投資信託だけではなく、貯蓄・保険も選べるなど、選択肢が多い
・原則、お金を引き出せるのは60歳になってから
・比較的リスクは低いが元本割れの可能性もある
自動積立定期預金
・毎月、自分で設定した金額が自動に積み立てられる定期預金
・給料の振込口座で設定すれば、使う前に自動で積み立てできる
・定期預金のため元本割れの心配はない
外貨預金積立
・外貨で積み立てる自動積立定期預金
・円の預金に比べて金利が高い
・為替リスクがあるため、円安になると元本割れになる可能性がある
いろいろな貯蓄方法があるので、
自分に合った方法を検討しましょう
上記で挙げたように貯蓄型保険以外にも、さまざまな貯蓄方法があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットをきちんと理解した上で、自分のニーズやライフステージに合った方法で貯蓄をしていくことが大切です。
保険を相談するならゼクシィ保険ショップへ
保険選びは、保障内容や保障期間、最適な保険料の支払額など、検討すべき要素が多々あります。自分に最適な保険選びが難しいという場合はプロに相談するのがお勧め。ゼクシ保険ショップでは、ライフプランニングでこれからかかるお金などを見える化し、そこから必要な保障を提案します。また、保険に限らず、家計管理や、資産形成など人生も相談できます。もちろん相談は全て無料。ぜひお気軽にご相談ください。
※掲載の情報は2022年4月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00495-2204











