結婚したときの保険の見直し方は?結婚の保険見直しステップ

更新日:2020/9/18
「結婚したら、ちゃんと保険のことを考えないと……」とは思っても、保険に加入する必要があるのか、あるいは、すでに加入しているけれど見直しの必要があるのかなど、どうしたらいいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、新婚夫婦に保険が必要な理由や、具体的な保険の見直し方法、夫婦で話し合っておくべきポイントなどをわかりやすく解説しています。何から始めたらいいかわからないという方は、まずこの記事を読んでみてくださいね。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
そもそも結婚したら、なぜ保険の加入・見直しをするの?

保険は、貯蓄が少ない新婚夫婦の強い味方!
結婚をすると、自分だけのことではなく配偶者の生活を考える必要があります。万一のとき、配偶者が生活に困らないよう準備しておきたいものですよね。
特に若い世帯の場合、十分な貯蓄がないケースも多く、また、一方が仕事を辞め家事や育児に専念する場合など、もしも家計を支える配偶者が死亡したときや、病気などで働けなくなってしまったときに、家賃や生活費が払えなくなってしまうといったことも起こりかねません。
そんなときに役立つのが「保険」です。保険に加入しておけば、いざというときに保険金や給付金を受け取ることができます。ですから、結婚をしたらまず、夫婦ふたりで保険をどうするのか考える必要があります。
妊娠前に、医療保険の検討を
また、妊娠・出産を考えている女性の場合は、妊娠前に医療保険への加入を検討することをおすすめします。
妊娠・出産時のリスクが高まるため、妊娠中は保険への加入を断られる場合があるからです。妊娠・出産自体は病気ではありませんが、帝王切開や切迫早産になったときは、入院が長引くなどして医療費が高くついてしまう場合があります。 ただでさえ妊娠・出産は女性にとって不安がいっぱいですから、安心して治療を受けられるよう金銭面は事前に備えておきたいものです。
医療保険に入っておけば、異常分娩(ぶんべん)などの際に、入院給付金や手術給付金を受け取ることができます。結婚するタイミングで保険の見直しを検討してみてください。
妊娠がわかってからの結婚をする場合、妊娠後でも加入できる保険も一部あるのでぜひ検討してみてくださいね。
加入を検討しているのなら、できるだけ早めに
保険商品は、多くの場合、年齢が上がるごとに保険料が高くなります。そのため、早めに目的に合った保険に加入しておくとよいでしょう。健康診断で何か指摘があったり、通院や入院歴があると、保険加入の時に条件が付いたり、保険料が高くなる、あるいは加入できないケースもあります。早いタイミングで、また、健康と診断されているうちに加入しておくと安心です。
【結婚の保険見直しSTEP 1】
まずはお互いの加入状況を確認しよう
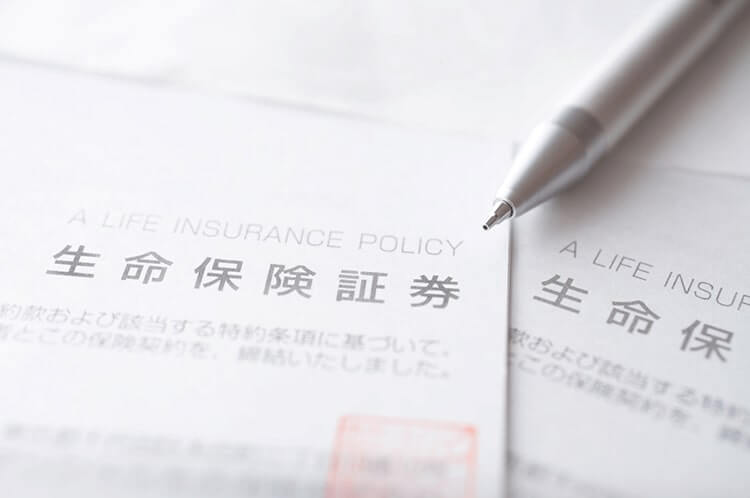
夫婦で確認することが何より大切!
まずは、夫婦それぞれがどんな保険に加入しているのか、それともまだ加入していないのかを確認しましょう。
| ケース別 | 確認ポイント |
|---|---|
| 保険に加入していない場合 | 家計の大黒柱となる人は、配偶者の生活を守るためにも、保険加入の検討を。共働きの夫婦の場合は、夫婦双方で加入の検討を。 |
| 子どもがいない場合 | 万一のときでも配偶者が働けるケースが多いとはいえ、貯蓄額に不安があれば、保険料の負担が少ない最低限の保険に加入するという手も。 |
| 職場・親戚の義理で保険に加入した場合 | 職場・親戚の義理で加入していた李親が保険をかけてくれていたりすると、必要な保障と合っていない場合も。結婚を機にきちんと見直しを。 |
| 保険には加入しているが、どんな保障なのかわかっていない場合 | よくわからない保険にお金を払い続けるのはもったいないもの。保険会社に確認し、その保障で十分か、保険料は割高ではないかなど確認を。 |
| 独身時に加入した保険を継続する場合 | 万一のときに請求漏れが発生しないよう、配偶者が保険の内容について把握しておくことが肝心。保険証券の保管場所なども確認を。 |
【結婚の保険見直しSTEP 2】
今後のライフプランを考えて、必要な保障を知ろう

結婚したら、将来子どもは何人欲しいのか、マイホームの購入はどうするのかといった、ライフプランを夫婦で相談しておきましょう。ひとりで漠然と考えるのではなく、夫婦ふたりの問題ですから、ふたりで話し合うようにしてください。
子どもの人数、マイホームを購入するかどうかがある程度決まれば、今後どのくらいの額のお金が必要かといったマネープランを立てやすくなります。 「子どもは2人で、マイホームを購入する」と決めたら、次に「いつまでにいくら貯めておくべきか」を話し合います。 その上で、万一のとき、貯蓄や公的制度、今後の収入などでカバーしきれない額を保険で補うようにすれば、もしものときでも安心です。
ライフプランをあらかじめ立てておくと、生涯に必要なお金が見えてくるので、保険の見直しもしやすくなります。 ぜひ結婚のタイミングでお互いの考えを整理してください。
ただ、具体的にいくら必要かを自分たちだけで試算したり公的制度を調べたりするのは難しいですよね。その場合は、保険の相談サービスを利用すると安心です。「具体的にどう考えればよいのかわからない……」といった漠然としたお金の悩みでも、気軽に相談してみましょう。
【結婚の保険見直しSTEP 3】
タイプ別:万一のとき、どのくらいのお金が必要か考えよう

万一のときに必要な3つの費用とは?
保険の加入・見直しをするときは、死亡保障がいくら必要なのかを把握しておくことが重要です。それぞれの家庭によって、必要な死亡保障は異なりますが、 共通して用意しておきたい費用が、葬儀費用、家族の生活費、子どもの教育費用です。
日本消費者協会の調査によると、葬儀にかかる費用は平均約195万円です。*1
残された家族の生活費は、現在の生活費の70%を掛けた金額を基準に考えましょう。*2
子どもの教育費は、幼稚園~高校まで公立、大学が私立だった場合、約1043万円必要です。*3
これらの金額が必要な死亡保障を考える際のベースとなります。次に、万一の時に各家庭によって適用になる公的制度が異なりますので、詳細と注意点を見ておきましょう。
共働き家庭の場合
子どもがいない共働き家庭の場合、それぞれに収入があるので、万一のときも人によっては収入や貯蓄で生活を賄える場合があります。 保障が必要だとしても子どもがいる家庭に比べれば、その額は少ないでしょう。
手厚い保障であればあるほど、当然保険料は高くなります。必要以上の保障を準備する必要はありませんので、自分たちに本当に必要な保障額はいくらなのかをきちんと計算して加入を検討するようにしてください。
会社員、公務員、自営業者など働き方を問わず、子ども(18歳到達年度の末日までの子。障害がある場合は20歳未満)がいる家庭の場合は、遺族は「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
夫が死亡し、妻と子ども1人が残された場合、約100万円が受給できます。*4
会社員や公務員など厚生年金に加入している場合、遺族は上記の金額にプラスして「遺族厚生年金」を受け取ることができます。遺族厚生年金は、子どもがいない場合でも受け取ることができます。また、受け取れる金額は死亡した人の収入によって変わります。
このように、もらえる遺族年金の種類や金額は働き方や収入によって変わるので、確認が必要です。
専業主婦(夫)家庭の場合
子どもがいない場合は、配偶者に万一のことがあっても働きに出ることが可能ですが、再就職や引っ越しなどのために費用がかかるので、生活を立て直すための資金は準備しておきたいところです。
小さい子どもがいる場合は、フルタイムでの勤務が難しいことが多いので、 余裕を持った資金計画を立てておきましょう。また、専業主婦(夫)家庭の場合、遺族が生活に困ることが考えられますので、 貯蓄や公的制度でカバーしきれない部分は、民間の生命保険で備えることを検討しましょう。
自営業の場合
自営業は、会社員や公務員ほど社会保障が手厚くありません。子どもがいる場合、遺族基礎年金を受給できますが、子どもがいないともらえません。 また、会社員や公務員とは違って遺族厚生年金も死亡退職金などもありませんから、その分民間の生命保険で備えておく必要があります。
【結婚の保険見直しSTEP 4】
ふたりの家計に合った保険料を考えよう

保障内容と保険料のバランスが大切
いくら保障の手厚い保険が安心だからといって、保険料を捻出するために日々の生活費を切り詰め、子どもの教育資金や住宅購入資金が貯められないのは考えものです。保険に加入する場合は、必要保障額と保険料のバランスを考えた上で加入するようにしましょう。
保険金は多いほど安心ですが、月々支払う保険料のために家計が圧迫されていては本末転倒です。反対に、現在の生活を十分に楽しむことだけを考え、 将来への備えを何も用意しないと、いざというときに自分たち家族が困ることになってしまいます。
家計の範囲内で、現在の生活の質を落とさず、 将来に対する備えも怠らないようバランスを考えて保険に加入すれば、将来に対する安心も現在の安定も、両方を手にすることにつながります。
加入の判断は、「納得できる商品かどうか」
保険相談に行けば、必要な保障額や最適なプランを提示してくれますが、無理のない保険かどうかは、ご自身の経済力から判断するよう心掛けましょう。
保障内容や保険料に不安があれば、その旨を伝えて、再度じっくりと検討するようにしましょう。保障内容も保険料も、納得できるものに加入することが大切です。
保険料は長い年月をかけて支払い続ける大きな買い物です。焦りは禁物ですよ。
【結婚の保険見直しSTEP5】
入って終わりはNG!結婚後も、イベントごとに見直しを

見直しタイミング:家を購入したとき
結婚後は、子どもの誕生や住宅購入などでライフスタイルが変化していきます。その場合、必要な死亡保障額も変わり、自分に合った保険も変わるため、 ライフイベントごとに保険の見直しをするようにしましょう。
住宅ローンを組んで自宅を購入した場合、団体信用生命保険(団信)に加入することで、すでに契約している保険を減額することができます。 必要保障額を見直せば、月々の保険料を減らせる可能性があるので、住宅購入も保険を見直しするいい機会となります。
子どもが独立すれば、大きな保障は必要ではなくなります。このとき保険を見直して、保障額の小さい保険に乗り換えれば、保険料を抑えることができます。
見直しタイミング:子どもが生まれたとき
子どもが誕生すると、養育費や学費などを準備する必要があるため、家計を担う人に万一のことがあった場合の経済的リスクが高まります。結婚したときの保険のままだと、子どものための保障が足りなくなる場合があるので、死亡保障を上乗せしたり、学資保険に加入するといった備えを検討しましょう。
見直しタイミング:働き方が変わったとき
転職をしたりどちらかが専業主婦(夫)になったりした場合も、年収が変わるため、今まで通りの保険(保障額)では高すぎる、あるいは低すぎるといった場合があります。フルタイムで働いていた時に加入した保険はその当時では、十分な保障金額だったけれど、子どもが誕生して専業主婦(夫)になったので、現在はその保障金額だけでは足りない、ということも起こり得るでしょう。世帯の収入に変化があったときも、現在加入している保険を見直す必要があります。
結婚すると、備えておくべき保障も独身の頃とは変化します。いざというとき困らないためにも、結婚のタイミングで早めに保険の加入・見直しを検討することをおすすめします。
「保険の知識が全くないから何から相談していいか……」
「今後どのくらいお金が必要かわからず、なんとなく不安」
「相手の今の保険のこと、貯蓄額のこと、何も知らないな」
そんな漠然とした悩みを抱えている人は多いはず。ゼクシィ保険ショップでは、無料でライフプランニング相談を行っています。 もちろん相談は何度でも無料。新婚ならではの悩みを抱えたご夫婦のライフプランニングを数多くサポート。 ふたりにとってどんな保険が必要なのかだけでなく、貯蓄のこと、将来の子どもの教育費やマイホーム購入など、ライフプランに合わせたふたりだけの家計プランも作成します。ぜひ一度相談してみてくださいね。
※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00307-2209










