個人事業主の保険とは?会社員との違いや保険の種類を解説

更新日:2023/05/30
独立して事業を営む個人事業主の場合、会社員とは加入すべき保険が大きく異なります。この記事では、保険加入を検討している個人事業主や、これから個人事業主になろうと考えている人に向けて、会社員の保険との違いや、検討すべき保険について解説していきます。該当する人は、ぜひ役立ててください。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
個人事業主の社会保険
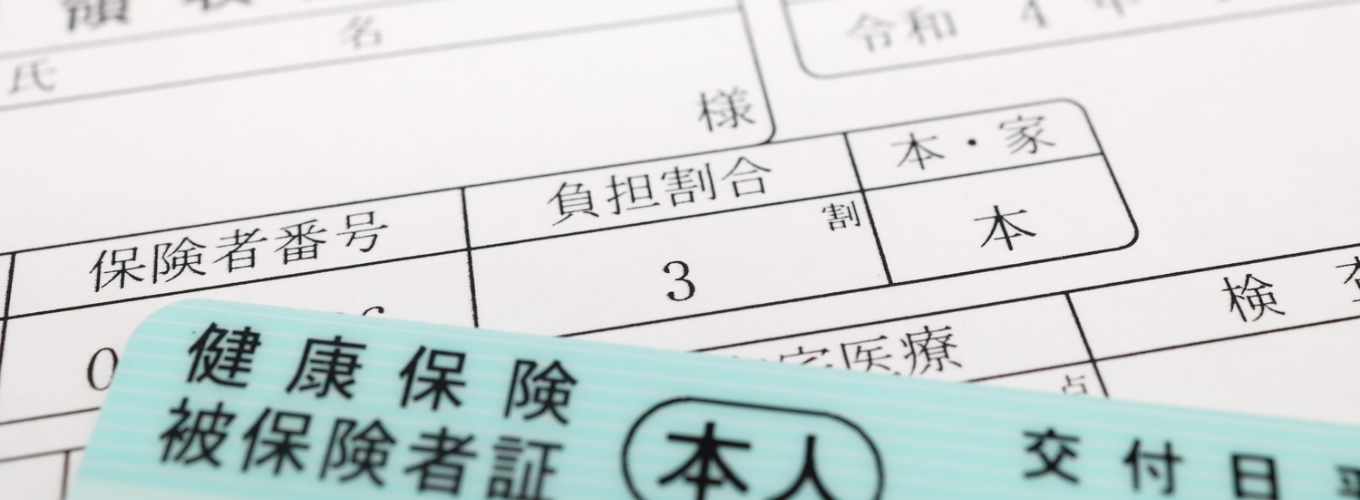
まずは、個人事業主が加入できる社会保険を整理しておきましょう。社会保険とは、病気やケガ、失業、労働災害などに備えるための公的保険制度です。社会保険の中にもさまざまな種類がありますが、そのうち個人事業主が加入できるのは、原則、国民健康保険、介護保険、国民年金の3つです。また、会社員の場合、それぞれの保険料は企業と従業員が折半して支払いますが、個人事業主の場合は、全額自己負担で支払います。
健康保険
健康保険は、病気やケガのため病院で治療した際の医療費を補填(ほてん)する制度です。成人の場合は、一般的に「健康保険証」を提出することで自己負担が3割で済むなどの仕組みとなっているものです。健康保険のうち、通常個人事業主が加入するのは「国民健康保険」です。国民健康保険にも、市区町村などが保険者となる「市町村国保」と、業種ごとの「国民健康保険組合(国保組合)」があります。国民健康保険の保険料は、世帯ごとの加入者数や収入、年齢などを基に算出されます。
国民年金保険
一般的に、日本の公的年金制度は「3階建て」といわれます。1階部分に相当するのが「国民年金」で、その上に会社員・公務員など加入する「厚生年金」があり、さらにその上に企業ごとに制度化している「企業年金」が乗っているというわけです。働き方によって受け取れる年金が異なりますが、個人事業主は1階部分である国民年金のみを65歳以降に「基礎年金」として受け取ります。
介護保険
介護保険は、高齢者などの介護を社会全体で支えるための制度。原則40歳になった時点で加入し、介護保険料を納めることになりますが、加入している健康保険と一緒に徴収されるため、個人事業主の場合は国民健康保険と一緒に徴収されます。
会社員とは異なる個人事業主の社会保険の特徴

では、どのような点で個人事業主の社会保険は会社員と異なるのか、その特徴を確認しておきましょう。
保険料は全額自分で支払う
会社員であれば、社会保険全般で会社が保険料の半分を負担してくれます。それに対して個人事業主の場合は、保険料を全額自己負担で支払う必要があります。ただし、社会保険料は全額、確定申告の際に所得から控除ができます。
雇用保険がない
会社員は、雇用保険に加入しています。そのため、失業した際には、基本手当が受け取れるほか、育児休業給付、介護休業給付などの受給もできます。これに対して、個人事業主は雇用保険に加入できないので、失業しても基本手当は受け取れず、育児休業給付や介護休業給付なども対象外となります。
傷病手当金がない
傷病手当金とは、病気やケガなどで働けなくなったときに通常給与の3分の2程度が受け取れる健康保険の制度です。この傷病手当金に関しても、個人事業主が加入する国民健康保険にはありません。従って、個人事業主が働けなくなった場合でも傷病手当金は支給されません。
労災保険がない
労災保険は、仕事中や通勤途中に起きた出来事を原因とするケガや病気、障害、または死亡した場合に給付を行う制度。この労災保険も雇用されている立場の人を対象とするため、原則、個人事業主は加入できません。ただし、例外として中小事業主や一人親方など、特定の個人事業主が労災保険に加入できる特別加入の制度もあります。
受け取る年金が少ない
すでに触れたように、老後に受け取れる老齢年金の年金額に関しても、会社員と個人事業主では異なります。会社員の場合、基礎年金に加えて厚生年金が受け取れます。一方、個人事業主が受け取れるのは基礎年金のみのため、会社員に比べて年金は少額です。また老齢年金に加えて、遺族年金や障害年金に関しても少なくなります。
個人事業主は生命保険加入を検討すべきである
生命保険は面倒と、先送りにしがちです。とはいえ、雇用保険や労災保険がない、傷病手当を受け取れない、年金が少ないなど、個人事業主は会社員に比べて保障が薄くなっています。そのため、なるべく早急に各種保険加入を検討するのが賢明です。
個人事業主が病気・ケガに備える保険

では、個人事業主はどのような保険に加入すべきなのでしょうか。中でも加入の必要性が高いと思われる保険を見ていきましょう。
医療保険
医療保険は、病気やケガによる入院や手術で生じる医療費に備えるための保険です。健康保険加入者の場合、医療費の一部を負担してもらえますが、医療保険に加入しておけば、健康保険では賄いきれない部分に関しても備えることができます。医療保険の保険商品の内容は多岐にわたるほか、通院・がん・三大疾病など、細かくプラン設計ができるため、自分に合った保険が確保できるようになっています。
生命(死亡)保険
生命保険は、保険加入者に万が一のことがあった場合に、残された家族のためのお金を保障する保険です。生命保険の中にも、定期保険、終身保険、養老保険、収入保障保険などいくつかの種類があります。どのタイプに加入する場合でも、会社員よりも遺族年金の金額が低めな個人事業主は、保障を高めに設定する必要性が高いです。
●定期保険
一定期間だけを保障するタイプの保険。子どもが自立するまでの間など、必要なタイミングだけ保険をかけることができます。解約返戻金や満期保険金などが受け取れない掛け捨て型の商品もあります。
●終身保険
解約しない限り、加入してから被保険者が亡くなるまで一生涯保障が続くタイプの保険。途中で解約した場合には、払い込んだ保険料などに応じて「解約返戻金」を受け取ることができるため、貯蓄性を兼ね備えています。
●養老保険
保険期間中に万が一のことが起きた場合に、死亡保険金が受け取れるのに加えて、存命のまま満期を迎えたときには、死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れるという仕組みの保険です。ただし、保険料はかなり割高となります。
●収入保障保険
保険期間の経過とともに受け取れる保険金の総額が徐々に減っていく仕組みの保険。毎月の給料のように一定額ずつ分割で受け取れるため、残された家族が家計を管理しやすくなるのも特徴です。
就業不能保険
病気やケガで働けなくなった際に収入が途絶えるリスクに備えるための保険です。所定の就業不能状態になると保険金が受け取れます。支払い条件は、病気やケガの種類にかかわらず、免責期間を超える入院や在宅医療が対象になるものと、三大疾病や五大疾病、要介護などに限定されているものなど、商品によってさまざまです。傷病手当金を受給できない個人事業主は、病気などで働けなくなると途端に家計に支障を来たします。会社員以上に、就業不能保険の加入の必要度は高いでしょう。
個人事業主が老後に備える保険

国民年金基金
「国民年金基金」とは、個人事業者がゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に上乗せする給付を行う公的な年金制度。国民年金基金に加入すれば、厚生年金が受け取れない個人事業者でも、年金を2階建てにすることが可能になります。掛け金の上限は、月額6万8000円(iDeCoとの合計額)。また掛け金は全額、所得控除の対象となり節税効果が大きいのがメリットです。
付加年金
「付加年金」は名前の通り、通常の年金に付加できる年金。通常の年金保険料に月400円の付加保険料を上乗せすることで、将来受け取れる年金額を増やせるという仕組みです。具体的には、受給する際に、年間で200円×付加保険料納付月数が上乗せされます。ただし、国民年金基金に加入していると、付加年金は利用できません。
個人年金保険
個人年金保険は、将来のための資金を計画的に準備できる民間の保険。働いている間に保険料を払い込み、老後になったら保険料に応じた年金を受け取るという仕組みです。公的年金などでは老後の生活資金が不足しそうな場合に、それを補う目的で加入します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、老後資金づくりを目的とする年金制度の一つ。加入者が掛け金を拠出し、自分で金融商品を選んで運用を行い、積み立てた資産を老後に受け取るという仕組みです。そのため運用の成績によって、将来受け取る金額が変わってきます。受け取るのは原則60歳以降となっています。iDeCoの最大の特徴は、拠出時・運用時・受取時の3つのタイミングで節税効果が得られるということです。
個人事業主が保険を検討するときのポイント

最後に、個人事業主が保険を検討する際に気を付けるべきポイントを紹介します。
扶養という仕組みがない
会社員の健康保険や厚生年金は、条件を満たせば配偶者や子どもを扶養に入れることができ、扶養に入れた人の保険料を負担する必要はありません。それに対し、個人事業主が加入する国民年金や国民健康保険には扶養家族の概念がありません。そのため個人事業主は、配偶者や子ども全員分の保険料を支払う必要があります。
会社を辞めた後2年間は健康保険の任意継続ができる
会社を辞めて個人事業主になる場合、申請手続きを行えば、勤めていた会社で加入していた健康保険を継続することができます。ただし、任意継続ができるのは2年間のみ。また、会社員時代とは異なって、退職後は保険料を全額負担することになる点も注意が必要です。
迷ったらプロに相談を
会社員に比べると、個人事業主は病気やケガに備える保障や老後の年金が手薄になりがち。そのため、不足になりそうな部分に関しては、自分で保険に加入していく必要が高くなります。ただし、いざ保険を選ぼうといろいろ調べてみると、疑問点や不安な点が出てくることが多いでしょう。そういったときには、プロに相談すると、疑問点も解決し、自分に合った保険選びができることにつながる場合もあります。
ゼクシィ保険ショップでは、保険だけでなく、ライフプランニングやマネープランニングについてもまとめて相談できます。さらに何度相談しても無料です。保険の加入を検討している個人事業主の方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか?
※掲載の情報は2023年5月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00532-2305











