公務員に保険は必要ない?おすすめの保険やメリット・選び方を解説

更新日:2023/05/30
公務員は社会保障が手厚いため、生命保険加入の必要性は低いと言われます。とはいえ、公務員でも民間の保険が必要な場合があります。この記事では、公務員に保険が必要な理由や保険のメリットなどを解説していきます。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
公務員に保険が不要といわれる理由

公務員はさまざまな保障が得られることから、会社員や個人事業主に比べて保険加入の必要性は低くなります。まずは、公務員が受けられる保障を確認しておきましょう。
社会保障が手厚い
公務員の場合、ケガや病気で休職をすると、休暇取得から90日間は給与の全額が支給される「病気休暇」があります。また、90日を超えた分に関しても休職の形となり、1年間は給与の80%を受け取れます。さらに1年経過すると無給となりますが、「傷病手当金」として給与の約60%の金額を受け取れるなど、休職の際の保障が手厚くなっています。
高額療養費制度を利用できる
公務員に限らず誰もが利用できる制度ですが、「高額療養費制度」も療養時は大きな保障となります。これは、入院などによって1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合に、超過分が高額療養費として戻ってくるというもの。たとえば、年収が約370万~約770万円で、100万円の医療費がかかった場合、実質9万円前後の自己負担となるため、医療費の自己負担を軽減することができます。
一部負担金払戻金を受け取れる
公務員の場合、高額療養費に加えて「一部負担金払戻金」も受け取れます。これは、診療報酬明細書一件につき2万5000円を超える部分が支給されるという制度。一部負担金払戻金を受け取れば、最終的な自己負担は25,030円まで軽減されます。
団体保険への加入ができる
公務員が民間保険に入る必要性が低い理由として、「団体保険」に加入することができことも挙げられます。団体保険は、給与所得者などが会社や組合などさまざまな団体を通じて加入する保険。団体割引が適用されるため、個人で保険に加入するより割安な保険料で加入できるのがメリットです。また団体保険に家族保障を付けることで、家族の保障も受けられます。
公務員で保険に入る必要がある人

以上のように保障が手厚い公務員ですが、必ず保険に入らなくていいというわけではありません。公務員でも、保険加入を検討した方がよい場合があるので、そうしたケースを紹介します。
家族が増える予定がある人
自分にもしものことがあった時、家族を支えられるだけの備えが必要になります。そのためにどのくらいの保障を準備すべきかは、家族構成などによっても変わってきます。たとえば子供の数が増えれば、当然生活費や教育費も増えてきます。そのような場合は、保険に加入してプラスアルファで保障を確保しておくとよいでしょう。
貯蓄が少ない人
貯蓄があれば、さまざまなケースに対処できますが、公務員でも貯蓄額が少ない人は、保険で備える必要性が高くなります。とくに若いうちはなかなか十分な貯蓄を持てないことも多いでしょう。そうした場合も保険に入っておけば、病気になった場合などにも対応できるため、安心です。
先進医療の保障が必要な人
先進医療の技術料は全額自己負担となるため、先進医療を受けると高額な治療費がかかる傾向があります。治療の選択肢を広げるためにも先進医療に備えておきたいという人は、保険の加入を検討するとよいでしょう。
共済組合とは
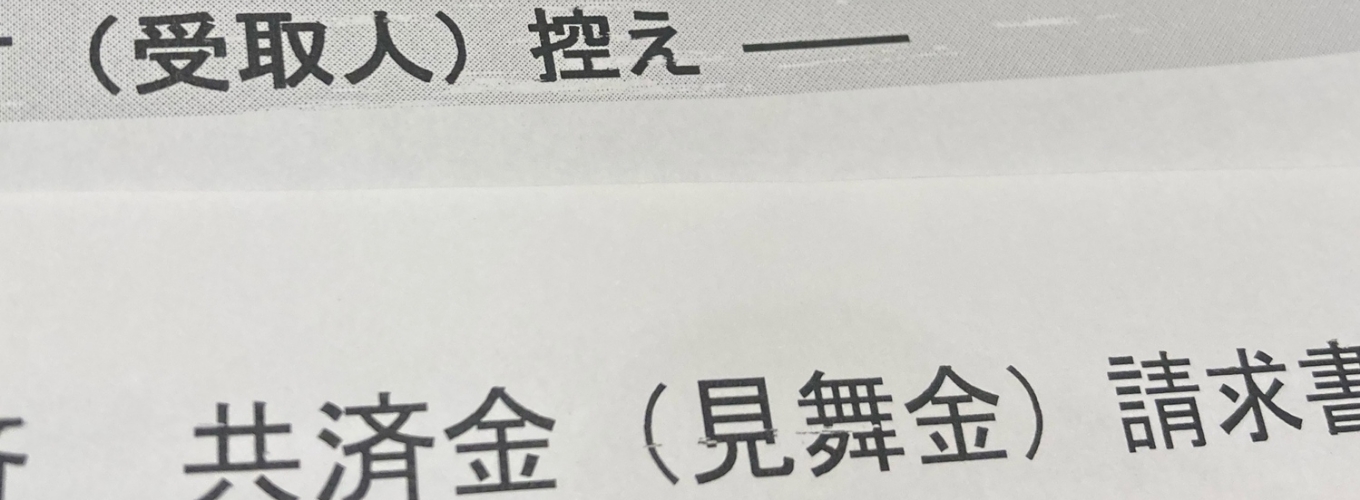
さらに公務員は、公的保障に加えて「共済組合」に加入しています。共済組合は、組合員やその家族にアクシデントがあったとき、給付金や年金を支給する制度。共済組合で受けられる給付は、大きく分けて「短期給付」と「長期給付」に分けられます。
短期給付
短期給付は、病気やケガ、出産に際して受けられる保険給付、休業給付、災害給付といった「法定給付」と、共済組合が独自に上乗せして支給する「附加給付」からなります。
長期給付
長期給付は、退職する場合や障害状態または死亡した場合に受け取れる年金や手当金。老齢給付、障害給付、遺族給付などがあります。
共済組合のメリット・デメリット
共済組合にはメリットとデメリットがあります。公務員が民間保険への加入を検討する場合には、このメリット・デメリットをきちんと理解しておく必要があります。
共済組合のメリット
共済組合は、組合員が負担する保険料だけでなく、国や地方公共団体などの負担金を財源としているため、保険料が割安。さらに保障内容の幅が広い点もメリットです。
共済組合のデメリット
共済組合の保障は最低限の保障内容となっています。さらに民間の保険のように、自分のライフスタイルや健康状態に合わせて保障内容を選べない点もデメリットと言えます。また、共済組合の保障は一生涯保障ではないことも把握しておく必要があります。
公務員の保険選びのポイント

公務員が保険を選ぶ際には、ここまで見てきた公務員が得られる保障をふまえつつ、以下のようなポイントに気をつけるとよいでしょう。
民間保険で公的保障の不足部分を補う
任意で加入する民間保険は、公的保障で不足する部分を補う目的で加入するものです。したがって、まずは自分がどのくらい公的保障を得られるのかを把握し、そのうえで足りなそうであれば、その分に関しては保険で備えるのがオススメ。たとえば、入院した際の差額ベッド代や食事代などについては保険でまかなうなどと考えておくとよいでしょう。
保険を見直す前提で選ぶ
必要な保険の種類や保障額は年代によって変わってくるため、保険は入ったら入りっぱなしではなく、年代に応じて適宜見直していくことが大切です。したがって、保険に加入する時点で、見直しができないような保険は避けた方が賢明です。
公務員におすすめの保険

では、公務員はどのような保険に入るとよいのでしょうか。ここでは、とくに公務員が加入を検討するとよい保険を紹介します。
終身保険
前述のように、共済組合の保障は一生涯ではありません。万一に備える保障を生涯保障にしたいという人は、終身保険へ加入するとよいでしょう。また終身保険は、途中で解約しても「解約返戻金」が戻ってくるため、貯蓄性のある保険がよいという場合も、終身保険がおすすめです。
終身医療保険
定年退職後は病気やケガのリスクが高くなるため、医療費の負担が大きくなる傾向があります。その点、若いタイミングで終身医療保険に入っておくと、リスクが高くなる定年退職後の保障を手厚くしつつ、退職後の医療費の負担を軽減することにつながります。
がん保険
公務員の場合。がんに関しての保障は充分とは言えません。そのため、がんへの備えを手厚くしたいという人は、がん保険に加入しておくとよいでしょう。
保険選びに迷ったらプロに相談も一つの手
保障が手厚い公務員ですが、だからといって保険のことをまったく考えなくてよいというわけではありません。まずは自分がどのような保障が得られるのかをきちんとおさえたうえで、不足しそうであれば、保険加入を検討するとよいでしょう。
保険選びに迷ったらプロに相談するのも一つの手です。ゼクシィ保険ショップでは、ライフプラン、年齢、収入、家族構成などに合わせた保険選びを相談できます。さらに何度相談しても無料です。ぜひ一度相談してみることをおすすめします。
※掲載の情報は2023年5月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00533-2305











