自営業の人・個人事業主が必要な保険とは?選ぶポイントや注意点を解説

更新日:2023/11/30
自営業の人や個人事業主は、会社員に比べて国の公的な保障が少ないといわれます。この記事では、自営業の人や個人事業主に向けて、会社員との公的保障の違いや、民間の保険への加入を検討するにあたって、おすすめの保険、加入する際のポイントと注意点について解説します。ぜひ参考にしてください。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
自営業の人と会社員の保障の違い
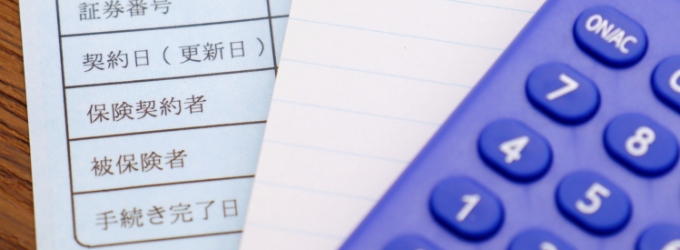
自営業の人と会社員の保障の違いとは何でしょうか?具体的に見ていきましょう。
「傷病手当金」がない
傷病手当金とは、病気やケガのために会社を連続して長期間休んだ場合に、4日以降最大1年6カ月間、休んだ日数に対して支給される手当のことで、支給額は給料の3分の2程度です。
傷病手当金は会社員が加入する健康保険から支給されるものであり、自営業の人が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。そのため自営業の人が病気やケガで働けなくなった場合には、収入をカバーする仕組みはなく、自分の貯蓄や保険で対応することになります。
老後の年金受取額が少ない
老後の公的年金制度をみると、会社員は国民年金と掛け金の半分を会社が負担してくれる厚生年金の2本立てで加入しています。それに対し、自営業の人には厚生年金がなく、国民年金1本になるため、老後に受け取れる年金額は少なくなります。
国民年金も厚生年金も亡くなるまで受け取れる終身年金であることを考えると、自営業の人の場合は、会社員に比べて、どうしても老後資金に対する不安が大きくなります。
家族のための遺族年金が少ない
国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったとき、遺族には遺族年金が支給されます。
会社員には、もしものときには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されますが、自営業の人は国民年金のみの加入となるため、遺族厚生年金の支給はありません。しかも、遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいなければ受け取ることができません。
自営業の人は、自分が亡くなった後の遺族の生活資金について、会社員よりもより一層の心配をしなければならないといえます。
自営業の人が加入する公的な保険は3つ
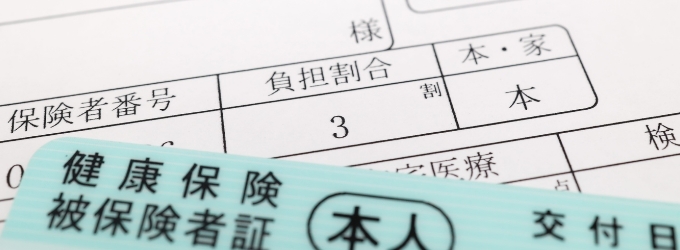
自営業の人が加入する公的な保険には3つあります。それぞれについて見てみましょう。
国民健康保険
自営業の人が加入する健康保険は国民健康保険です。国民健康保険は市区町村で運営されています。自営業の人は国民健康保険に加入する義務があり、加入することで病気やケガによる医療費の自己負担割合が原則3割となります。なお、加入手続きは、住んでいる自治体の役所で自分で行わなければなりません。
国民健康保険の保険料は前年の所得により決定され、会社員とは異なり、全額を自己負担する必要があります。
国民年金保険
国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全員が加入しなければなりません。国民年金には老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類の年金があります。
国民年金の保険料は、1カ月あたり1万6520円です(令和5年度)。なお、6カ月分や1年分などをまとめて前払いすると、保険料の前納割引があります。
会社員は国民年金に上乗せして厚生年金に加入していますが、自営業の人は国民年金のみの加入になります。
介護保険
介護保険は40歳以上のすべての国民に加入が義務付けられています。
要支援または要介護状態と認定されたときに、原則として1割の負担で介護サービスを受けることができます。ただし、40歳から64歳までの人は、特定の疾病により要支援または要介護状態と認定されたときに限られます。
保険料は、65歳未満の人の場合、健康保険の保険料に上乗せして徴収されます。
自営業の人が保険を選ぶポイントと注意点

次に自営業の人が保険を選ぶ際のポイントと注意点について見てみましょう。
働けなくなった場合に備える
まず考えなければいけないのは、病気やケガで働けなくなってしまった場合の収入に備えることです。会社員は有給休暇を使えば給料が受け取れますし、傷病手当金もあります。しかし自営業の人は有給休暇もなければ傷病手当金もありません。そのため、自営業の人は貯蓄や保険で備えるしかありません。
十分な貯蓄がなく、保険で備えたいという場合には、就業不能保険や所得保障保険が役に立ちます。
加入にあたっては、保険料、受け取れる保険金、保険金を受け取れるまでの期間などについて比較検討が必要になります。
老後のために備える
次に考えなければならないのは、老後の生活資金への備えです。
会社員とは異なり、自営業の人は国民年金保険のみの加入になります。老後に受け取れる年金が少なくなるため、自分で備える必要があります。保険で備える場合には個人年金保険が役に立ちます。
一定期間保険料を積み立て、老後に年金として受け取っていくのですが、途中で解約をすると元本割れをするデメリットもあるので注意しましょう。なお、一定の要件を満たせば確定申告で「個人年金保険料控除」が受けられるという税制上のメリットもあります。
自営業の人におすすめの保険の入り方

自営業の人におすすめの保険の入り方について、定期保険と終身保険という特徴的な2つの種類に分けて見ていきましょう。
定期保険
定期保険とは、保険期間が10年や20年などの一定期間で、死亡や高度障害に対する保障に備えることができる保険です。いわゆる「掛け捨て型」の保険で、貯蓄性がない(解約返戻金がない)ため、保険料がリーズナブルです。
自営業の人は会社員に比べて遺族年金が少ないので、子どもが社会人として独立するまでは高額な死亡保障が必要になります。そのため、まずは定期保険で備えると良いでしょう。
終身保険
終身保険とは、一生涯にわたり、死亡や高度障害に対する保障に備えることができる保険です。終身保障なので解約をしなければ必ず保険金を受け取ることができます。
また、定期保険とは異なり、解約した場合には、解約返戻金を受け取ることができます。そのため定期保険に比べて保険料が割高ですが、保障と貯蓄の両方を兼ね備えており、解約返戻金を老後資金として活用することもできます。
保険料がリーズナブルな定期保険と組み合わせて必要な保障を準備すると良いでしょう。
自営業の人におすすめの民間保険

それでは自営業の人におすすめの民間保険とは何か?具体的に見ていきましょう。
医療保険
医療保険とは、病気やケガなどでの入院・手術に対して、給付金を受け取ることができる保険です。自営業の人には会社員が受けられる「傷病手当金」がないため、加入を検討する必要があります。
医療保険には、がん・心疾患・脳血管疾患に備える三大疾病特約や先進医療特約などいろいろな特約を付加することができるので、必要なものを検討してみましょう。
また、2人に1人が罹患(りかん)するといわれている、がんの保障に特化した「がん保険」もあります。保険料は上がりますが、希望に応じて保障を厚くすることができます。
就業不能保険
就業不能保険とは、病気やケガなどによって働けなくなったときに、給付金を一定期間受け取ることができる保険です。就業不能の状態になったときに給付金が受け取れますが、保険会社によって就業不能状態の定義が異なりますので、確認が必要になります。
自営業の人には有給休暇や傷病手当金がありません。そのため、病気やケガなどで長期療養が必要となり、働けないということになれば、収入が大きく減少することが考えられます。万が一働けなくなったときの収入減に対する備えとして、加入を検討する必要性が高いといえます。
個人年金保険
個人年金保険とは、一定の年齢まで保険料を積み立てて、老後に年金として受け取ることができる保険です。自営業の人は会社員とは異なり国民年金のみとなるため、老後資金として自分で年金を準備することが必要になります。
個人年金保険には、「確定年金」「有期年金」「終身年金」など、さまざまな種類があります。
確定年金は、年金受取期間が10年や15年などの一定期間で、もしも被保険者(個人年金保険の対象になる人)が亡くなったときには、遺族が受け取ることができます。
有期年金は、年金受取期間が10年や15年などの一定期間ですが、被保険者が亡くなると、一般的には遺族が受け取ることはできません。
終身年金は、被保険者が生きている限り、年金を受け取ることができます。
火災保険・地震保険
自営業の人は、テナントを借りたり、自宅を店舗としたりする場合などもあるので、火災保険や地震保険への加入も検討しましょう。火災保険に加入していれば、仕事で使用している道具や備品などが、火災、風災、雪災、水災などで損害を受けた場合に、保険金で対応することができます。
地震による損害は地震保険で対応しますが、地震保険の対象は、居住用の建物と家財のみです。また、地震保険は単独で加入することができず、火災保険とセットで加入する必要があります。
確定申告の際に、火災保険の保険料は対象になりませんが、地震保険の保険料は地震保険料控除として所得控除の対象となり、税制上のメリットがあります。
不安があればプロに相談がおすすめ
自営業の人は会社員に比べると公的保障が少ないです。そのため、公的保障だけに頼らずにリスクに適切に備える必要があります。公的保障で不足する部分をカバーするのが民間の保険の役割です。
とはいえ、民間の保険は種類が多く、必要な保険を自分で選ぶのは大変です。
自分で選ぶのに不安がある場合や、詳しく知りたい場合には保険のプロに相談するのがおすすめです。
ゼクシィ保険ショップでは、保険に関することだけでなく、家計やライフプランニングについてもまとめて相談できます。さらに何度相談しても無料です。もちろんオンライン相談もできますので、保険の加入を検討している人は一度相談してみてはいかがでしょうか。
※掲載の情報は2023年11月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00559ー2311











