生命保険に相続税はかかる?節税対策になる?3つのポイントと注意点

更新日:2024/8/30
亡くなった人が生命保険に加入していた場合、相続税がかかるのか不安に思う人もいるでしょう。しかし、実際に相続税がかかるかどうかは保険金の種類や保険の契約形態、生命保険の金額によって変わります。すべての生命保険金に相続税がかかるわけではありません。
この記事では、生命保険と相続税の関係と課税ポイントをわかりやすく解説します。相続税以外の税金が課される可能性やその条件についても紹介します。生命保険にかかる不安のある人は、ぜひ役立ててください。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
生命保険金に相続税がかかる場合とかからない場合がある

生命保険金に税金がかかるかどうかは、保険金の種類や契約形態によって変わります。
<保険の契約形態>
・保険の対象者:被保険者
・保険会社と契約し、保険料を支払っていた人:契約者
・保険金を受け取る人:受取人
保険の対象者(被保険者)が亡くなった際に受け取る死亡保険金にかかる税金は、「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかです。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 契約者と被保険者が同じ | A | A | B | 相続税 |
| 契約者と受取人が同じ | A | B | A | 所得税・住民税 |
| 契約者・被保険者・受取人がそれぞれ違う | A | B | C | 贈与税 |
相続税として受け取る死亡保険金には非課税枠が設けられているため、必ずしも税金がかかるわけではありません。ここでは契約形態ごとにかかる税金の種類を解説していきましょう。
亡くなった人が自ら保険料を払っている場合は「相続税」
亡くなった人が自ら保険料を支払っていた、つまり契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は相続税の対象です。
ただし、死亡保険金を受け取る人や亡くなった人の配偶者や子どもなど相続人である場合、死亡保険金は一定額まで非課税になります。非課税枠については後述します。
保険料を払っていた人と受取人が同じ場合は「所得税・住民税」
保険料を払っていた人と保険金受取人が同じ場合は、死亡保険金は所得税・住民税の対象となります。
例えば、亡くなった人(被保険者)が母親で保険料を払っていた人(契約者)が父親、死亡保険金受取人も父親というケースが該当します。この場合、所得税の分類は「一時所得」の扱いとなります。
亡くなった人と保険料を払っていた人、受取人が全員違う場合は「贈与税」
亡くなった人と保険料を払っていた人、そして保険金を受け取った人が全員違う場合は、死亡保険金は贈与税の対象になります。
例えば、亡くなった人(被保険者)が母親で保険料を払っていた人(契約者)は父親、死亡保険金の受取人は子どもというケースが該当します。
相続税がかかる理由
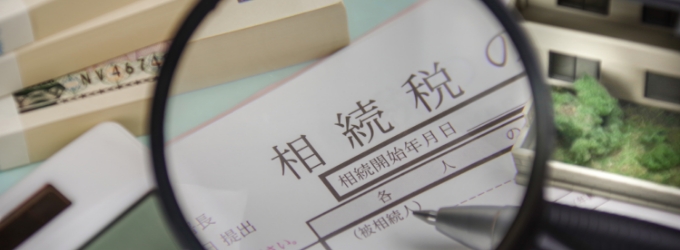
契約者と被保険者が同一の契約では、受け取った生命保険金(死亡保険金)に相続税がかかります。
一方、民法上で生命保険金は「受取人固有の財産」とみなされ、遺産分割協議の対象外となります。では、なぜ相続税がかかるのでしょうか。確かに死亡保険金は受取人固有の財産ですが、被保険者の死亡によって支払われます。そのため実質的には相続財産とみなされ、相続税の対象となります。
このように相続税がかかる生命保険金は「みなし相続財産」と呼ばれています。
参考:No.4105 相続税がかかる財産|国税庁
生命保険金に関する相続税の非課税枠

生命保険金(死亡保険金)の受取人が亡くなった人の相続人である場合、その生命保険金には一定の「非課税枠」が設けられます。受け取った死亡保険金が非課税枠内であれば、その保険金に対する相続税はかかりません。
非課税枠の金額は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
この「法定相続人」に含まれるのは、死亡した人(被保険者)の配偶者と子どもや親などの血族です。配偶者は常に法定相続人となりますが、血族には相続順位があります。
<相続順位>
第1順位:子ども、その代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、その代襲相続人(傍系血族)
例えば、亡くなった人に妻と2人の子どもがいれば、法定相続人は3人です。この場合、後順位の親や兄弟姉妹などは法定相続人に含まれません。また、法定相続人には相続放棄をした人や被保険者の養子(制限あり)も含めます。
非課税枠のない生命保険金もある
非課税枠が適用されるのは、以下の2つの条件を満たす死亡保険金に限ります。
・契約者・被保険者が同一の生命保険契約
・被保険者の死亡によって発生する死亡保険金や死亡給付金を被保険者の相続人が受け取る場合(相続放棄した受取人には非課税枠の適用はない)
従って、以下の保険金や給付金には相続税の非課税枠の適用はありません。
・満期保険金
・生存給付金
・解約返戻金
・個人年金保険の年金
・入院・手術などの給付金*
・リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金*
ただし、病気やケガ、重度の疾病に起因して支払われる入院・手術給付金やリビング・ニーズ特約の生前給付金はもともと非課税です。相続税の非課税枠が適用されなくても、そもそも非課税の給付金なので安心してください。
非課税枠を超えても基礎控除がある
受け取った生命保険金(死亡保険金)が相続税の非課税枠を超えている場合でも、受け取った遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税が課されることはありません。
相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
例えば生命保険に加入していた父親が亡くなり、母親と子ども3人が残された場合で計算してみましょう。
・法定相続人は4人(母親と子ども3人)
・相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×4人)=5400万円
・受け取った生命保険金は合計3000万円
・生命保険金の非課税枠は500万円×4人=2000万円
・その他の遺産が合計4000万円
・遺産総額は4000万円
この場合、受け取った生命保険金額(3000万円)は非課税枠(2000万円)以上ですが、遺産総額は4000万円となり、基礎控除額(5400万円)以下です。従って、非課税枠を超えていても基礎控除のおかげで相続税はかかりません。
生命保険の相続税に関する3つのポイント

ここでは、生命保険にかかる相続税のポイントを3つ解説していきます。
相続税は生命保険金にだけかかるわけではない
相続税は、受け取った生命保険金(死亡保険金)だけにかかるわけではありません。受け取った生命保険金にその他の預貯金や不動産といった相続財産を含めた、遺産総額から計算されます。
従って相続税の有無は、すべての遺産の合計額によって変わります。遺産の対象となる財産の種類や遺産の評価方法には専門的な知識が必要です。遺産の種類や金額が多い人は、税理士や税務署など専門家に問い合わせることも検討しましょう。
生命保険金の合計が「500万円×法定相続人の数」以下なら相続税はかからない
相続税の計算は容易ではありませんが、「生命保険金に相続税がかかるかどうか」は計算できます。受け取った生命保険金の合計額が非課税枠の「500万円×法定相続人の数」以下であれば、その生命保険金に関する相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人で、非課税枠は1500万円の場合。生命保険金の合計額が1000万円であれば非課税枠以下となるため、その生命保険金に相続税がかかることはありません。また、遺産が「生命保険金」だけで他に預貯金や不動産、株などの財産が何もなければ、遺産総額にかかる相続税もありません。この場合は、相続税申告も不要です。
ただし、生命保険金は非課税でも、他の相続財産が基礎控除額を超えていると相続税がかかる可能性がありますので注意が必要です。
相続税の税率は財産取得額により異なる
相続税の税率は「超過累進税率」を採用しているため、最終的な遺産総額によって税率が異なります。税率は以下速算表の通りです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | ― |
| 1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 2億円超3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 3億円超6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
相続税を計算する際は、課税遺産総額を各相続人の法定相続分に応ずる取得金額に分け、その取得金額に税率を掛けた金額から控除額を差し引きます。
こうして算出した「法定相続人ごとの税額」を合計した金額が相続税の総額となります。
参考:No.4155 相続税の税率|国税庁
生命保険の相続税に関する注意点

生命保険の相続税に関する注意点は以下の2つです。詳しく見ていきましょう。
法定相続人ではない「孫」にかかる相続税は1.2倍である
生命保険金(死亡保険金)の受取人を法定相続人以外の孫にしていると、その孫の相続税額が2割加算される、つまり1.2倍になるというルールがあります。
例えば、亡くなった人(被保険者)に配偶者や子どもがいるとします。この場合、法定相続人は配偶者と子どもで、孫は法定相続人になりません。生命保険金の受取人に孫を指定することはできますが、非課税枠は適用されません。また、この孫に相続税がかかる場合、その税額は1.2倍になります。
ただし、亡くなった人(被保険者)の子どもがすでに死亡していて、代襲相続によって孫が法定相続人となる場合は別です。この場合、法定相続人は配偶者と孫になるため、生命保険の非課税枠が適用されます。相続税額が1.2倍になることもありません。
相続税対策としての生命保険加入は慎重に検討する
生命保険金(死亡保険金)には非課税枠がある上、受取人固有の財産として遺産分割協議の対象外です。そのため、相続税対策に活用されることが多くなっています。
ただし、契約形態を間違えると相続税の非課税枠が適用されず、贈与税や所得税・住民税の対象になってしまう可能性があります。加入の際は契約形態や金額に気を付け、慎重に検討することが大切です。
生命保険で困ったらプロに相談を

生命保険の種類は多岐にわたり、死亡保険金を受け取れるものだけでも多数の商品が販売されています。選択肢が多いため自分に適した保険を選ぶことは難しく、受取時の税金関係など困る場合もあるでしょう。
特に生命保険は、残された家族の生活を支える大切な遺産となるため、慎重な判断が必要です。加入の際は、知識が豊富なプロに相談することをおすすめします。
保険金の種類や契約形態によって、生命保険金にかかる税金の種類は変わります。死亡保険の場合は相続税または贈与税、所得税・住民税がかかる可能性があり、相続税には非課税枠が用意されています。
生命保険金にかかる相続税の非課税枠は相続税対策に有効ですが、税金の対策を行う際は専門知識が必要となるため、可能な限り専門家に相談することをおすすめします。ゼクシィ保険ショップの窓口では、生命保険の相続税非課税枠を活用した相続税対策の相談を無料で受け付けています。各家庭の状況に合わせて適切な死亡保険や金額を案内できるため、死亡保険にかかる税金が気になる人はお気軽にご相談ください。
「近くに店舗がない」「対面相談には抵抗がある」という人には、自宅で話せるオンライン相談もご利用可能です。
※掲載の情報は2024年8月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00953-2408











