生命保険にトラブルはある?事例と防ぐ方法をわかりやすく紹介

更新日:2025/8/31
生命保険はご家族の安心を守るために大切な存在ですが、「複雑でトラブルが心配」と感じる方も少なくないでしょう。確かに、内容の理解不足や手続き上の誤りから、思わぬ問題が生じるケースがあります。この記事では、生命保険で起こり得る代表的なトラブル事例と、それらを未然に防ぐための具体的な方法をわかりやすく解説します。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
生命保険とは

生命保険とは、ご自身の死亡や病気・ケガといった万が一の事態に備えるための経済的備えです。多くの加入者が公平に保険料を負担し合い、いざという時に保険金や給付金を支え合う「相互扶助」の仕組みに基づいています。
就職や結婚、出産など、ライフステージが大きく変わるタイミングで検討される方が多く、人生の節目におけるリスクマネジメントの重要な手段です。契約内容は商品によって大きく異なりますので、保障範囲や条件を事前にしっかり把握することが大切になります。
生命保険で考えられるトラブルの事例
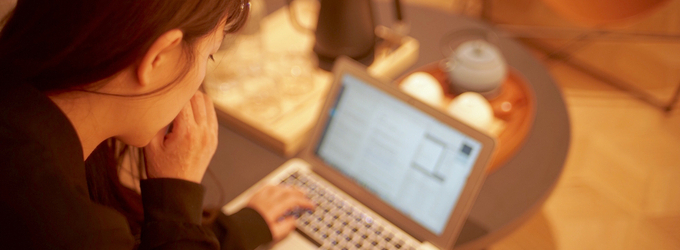
生命保険契約では、思わぬトラブルに発展するケースがあります。以下では、実際に起こり得る代表的な事例を3つご紹介します。それぞれのトラブルを防ぐための具体的な方法については、次の項目で詳しく解説しますので、合わせて参考にしてください。
思っていた保障内容ではなかった
契約時にパンフレットや説明で聞いていた保障内容と、実際の保険の保障内容が異なるというケースがあります。例えば、「特定の病気は必ず保障される」と思い込んで加入したのに、実は約款(契約の詳細な規則)にその病気が「保障対象外」と明記されていた場合などが挙げられます。
このような齟齬(そご)は、営業担当者の説明不足や、加入者側がパンフレットや約款を十分に確認せずに契約してしまった場合に発生しがちです。特に、医療保険や特定疾病保障保険では、対象疾病の定義や免責事項を厳密にチェックすることが不可欠です。「重要事項説明書」は必ず目を通し、不明点はその場で解消しておきましょう。
もらえると思った保険金が支払われなかった
実際に給付金を請求したにもかかわらず、支払いを拒否されるトラブルも多く見られます。理由の1つとして「免責事由」に該当するケースがあります。
免責事由とは、保険会社が保険金の支払い義務を負わないと契約で定められた特定の状況や原因のことです。代表的な例としては、契約後一定期間内(通常は1~3年)の自殺、保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合などが挙げられます。
その他にも、事故や病気が契約前から存在した「既往症」と判断された場合や、請求手続き上の不備(必要書類不足や期限経過)も支払い拒否の原因となります。保険金を受け取る権利が発生する条件は、約款に細かく規定されていますので、加入時に確認しておくことが重要です。
保険会社のほうから契約を解除された
保険契約後に、保険会社から一方的に契約を解除されるケースもトラブルとして挙げられます。この背景には、ほとんどが「告知義務違反」が存在します。
告知義務とは、加入時に健康状態や既往歴、家族歴などを正確に告げる義務であり、故意だけでなく過失による誤記載でも「違反」とみなされます。例えば、過去に大きな病気を患っていたにもかかわらず申告を怠ったり、持病の重症度を軽く記載したりすると、発病後に解除されるリスクが高まります。
解除されると、払い込んだ保険料は返還されますが、保障は消滅します。また、その後の再加入時には「告知義務違反歴」があるとして保険料が割り増しされるか、加入自体を断られる可能性もあります。
生命保険のトラブルを防ぐための3つの方法

トラブルに遭わないためには、事前の対策が何よりも重要です。ここでは、特に心がけたい3つの具体的な方法をご紹介します。
保険の内容をよく理解してから契約する
何よりも大切なのは、契約前に保障内容を確実に理解することです。パンフレットや約款(特に「支払事由」「不支払事由(免責事由)」の箇所)、そして契約の概要を示す「重要事項説明書」を必ず熟読しましょう。
これらの書類は、保険の保障範囲や、保険金が支払われない条件を具体的に記載しています。説明を受ける際や書類を読む中で、少しでも疑問や不明な点があれば、必ず保険会社の担当者やファイナンシャルプランナーにその場で確認してください。わからない点はきちんと解消しておくことが、後のトラブル回避につながります。
ありのまま正確に告知する
生命保険加入時に提出する「告知書」への記入は、正確に行いましょう。過去の病歴や現在の健康状態、喫煙習慣などについて、事実と異なる内容を記入することは告知義務違反となり、契約解除や保険金不支払いの重大なリスクを招きます。
曖昧な点があれば、適当に記入せず、かかりつけ医に相談するか、保険会社の担当者に記入方法を確認することをお勧めします。告知項目は保険商品によって異なりますが、正直に申告することが長期的な安心につながります。
クーリング・オフ制度について確認しておく
クーリング・オフ制度は、契約締結後でも一定期間内であれば無条件で解約ができる制度です。一般的には「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から8日以内が原則ですが、保険会社によっては10~30日まで延長している場合もあります。ただし、以下のケースは制度適用外となるため注意が必要です。
・契約に際して医師による告知診査を受けた場合
・保険期間が1年以内の短期契約の場合
・既存契約に特約を追加した場合
クーリング・オフの可否や詳細な手続き方法は保険会社や商品により異なりますので、契約時に必ず確認し、案内書類は大切に保管しておきましょう。
生命保険を選ぶときのポイント

生命保険を検討する際、特に以下のポイントに留意することで、より安心できる選択が可能になります。それぞれの詳細を見ていきましょう。
健康状態に不安がある人向けの保険もある
持病がある方や過去に大きな病気をされた方など、告知内容に不安がある場合、「引受基準緩和型(限定告知型)保険」や「無選択型保険」という選択肢があります。引受基準緩和型保険は、告知項目が一般的な保険より少なく、特定の病気に関する質問のみに答えるタイプです。無選択型保険は、健康状態に関する告知が一切不要なタイプです。これらの保険は、その分保険料は割高になる傾向がありますが、通常の保険に加入が難しい方にとっては貴重な選択肢となります。健康上の理由で諦める前に、こうした商品の存在も知っておきましょう。
空白期間ができないよう注意する
現在の保険から別の保険に乗り換える際には、「保障の途切れ(空白期間)」が発生しないよう注意が必要です。新しい保険の責任開始日(保障開始日)よりも前に従来の保険を解約してしまうと、その間に万一の事象が起きても一切の給付が受けられません。特にがん保険などでは、責任開始日から90日間は保障が適用されない「免責期間」が設定されている場合もあります。待機期間の有無や長さも事前に確認し、計画的な乗り換えを心がけてください。
迷ったらプロに相談する
生命保険は商品数が多く、約款や条項も複雑で、ご自身だけで最適な選択を判断するのが難しいと感じる方も多いでしょう。そんな時は、ファイナンシャルプランナー(FP)や保険ショップのアドバイザーなど、専門家の力を借りることをお勧めします。プロの視点から必要な保障額や保障内容のポイントを整理してもらうことで、不要な保障を避け、本当に必要な保険を効率的に選ぶことが可能になります。
保険の内容をよく理解し、迷ったらプロに相談を
生命保険は家族の生活を守る大切な仕組みですが、「保障内容の相違」「保険金の不支払い」「契約解除」といったトラブルが生じる可能性があります。こうしたリスクを防ぐためには、契約前に約款や重要事項説明書を熟読して内容を確実に理解すること、加入時には健康状態をありのまま正確に告知すること、万が一のためのクーリング・オフ制度の内容を把握しておくことが不可欠です。また、保険選びの際には、ご自身の健康状態に合った商品の選択や乗り換え時の空白期間回避を心がけ、迷ったら専門家への相談も検討しましょう。
ゼクシィ保険ショップでは家族構成や今後のライフプランに合わせた保険選びのアドバイスが受けられます。相談は無料でオンラインでの対応も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
※掲載の情報は2025年8月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-01005-2508











