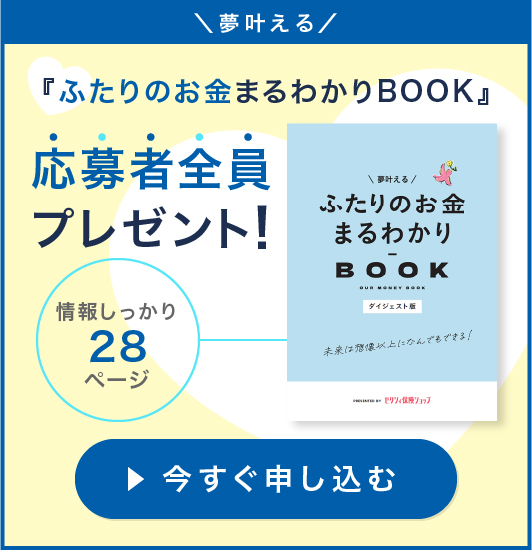吸引分娩は保険適用される?保険の種類や注意点を解説

更新日:2025/2/28
出産は女性にとって非常に重要なライフイベントですが、異常分娩になってしまうことも。「吸引分娩(ぶんべん)」もその一つですが、母子の安全を確保するために医師が行う治療行為の一環です。とはいえ、吸引分娩に保険は適用されるのかどうか不安に思う人もいるのではないでしょうか。本記事では、吸引分娩の保険適用、出産時に利用できる一時金、吸引分娩に保険を活用する際の注意点などについて詳しく解説します。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる


吸引分娩とは

吸引分娩とは、出産がスムーズに進まずに難産になったときに、医師が吸引カップを使って赤ちゃんを引き出す分娩方法です。金属製のハードカップやシリコン製のソフトカップといった吸引カップを赤ちゃんの頭部に吸引し、その力で出産を促します。この方法は、引き出す力が強くないため、場合によってはおなかから圧力を加えることもあります。吸引分娩後、赤ちゃんの頭部の形が気になることがありますが、心配な場合は専門の医師に相談すると安心です。
吸引分娩は保険適用になる?
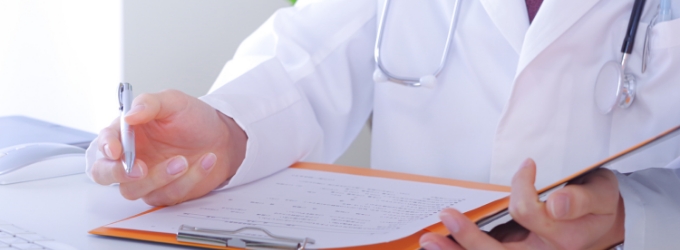
正常分娩による出産は、2025年現在公的保険制度の対象外です(※)。それに対して吸引分娩は、治療行為を必要とする異常分娩に該当するため、公的保険の適用対象となります。民間保険の場合でも保障対象となることが多いですが、契約内容によって保障範囲や給付内容が異なります。
※2026年から健康保険対象にするべく、政府が検討中
公的医療保険が適用された場合の自己負担額
吸引分娩が異常分娩として医師によって判断されると、公的保険の対象となり、自己負担額は3割となります。また吸引分娩以外にも、鉗子(かんし)分娩、帝王切開や会陰切開といった異常分娩は、公的保険制度の対象です。ただし異常分娩の場合でも、分娩前後に必要となる母子へのケアや入院中の介助などにかかる費用については自己負担となる点は注意が必要です。
吸引分娩の民間保険の適用について
民間の医療保険の場合でも、吸引分娩は異常分娩として扱われるため保障対象となります。吸引分娩が保障対象となった場合、入院日数に応じた入院給付金が支給されることが一般的です。医療保険に女性疾病特約が付帯されていれば、女性疾病入院給付金が上乗せされることもあります。ただし、保障内容や給付金額は保険契約によって異なるため、契約内容をしっかり確認することが重要です。
吸引分娩は自費になる場合がある
吸引分娩は分娩中にトラブルが発生し、母子の生命に関わる事態となったときに実施されるため、通常は保険が適用される医療行為です。しかし、医師が吸引分娩を「正常分娩の範囲」と判断する場合は、保険は適用されません。そのため、吸引分娩であっても自費となる場合があることを覚えておく必要があります。
出産時に利用できる一時金とは

吸引分娩に限らず、出産時には、さまざまな公的一時金が受けられる可能性があります。受け取り忘れることがないよう、それぞれの制度について押さえておきましょう。
出産育児一時金
国民健康保険や健康保険の被保険者が出産すると、子ども1人につき50万円の「出産育児一時金」が支給されます。医療機関が受取代理制度に対応している場合、この一時金は医療機関が直接受け取り、出産費用に充当されるため、本人は差額のみを支払えばよく、立替払いの必要はありません。一方、受取代理制度に非対応の場合は、一度全額を支払い、後日振り込まれます。受給には健康保険組合への申請手続きが必要のため、事前に確認しておくことが重要です。
出産手当金
「出産手当金」は、出産のために会社を休んだ場合に受け取れる手当で、勤務先の健康保険から支給されます。支給額は1日当たり給与の3分の2で、「標準報酬月額の平均額÷30日×2/3」という式で計算されます。支給期間は合計98日間で、予定日を過ぎた場合もその日数が含まれます。受給には「出産手当金支給申請書」の提出が必要です。なお、出産手当金は健康保険加入者のみが対象で、国民健康保険にはこの制度はありません。
育児休業給付金
「育児休業給付金」は、育児休業後に復職することを条件に、雇用保険から支給されます。支給額は休業開始時の賃金月額の最大67%相当で、2カ月ごとに支払われます(181日目からは50%相当)。給付金は非課税で、育児休業期間中の保険料も全額免除されます。申請後、最短で3カ月程度かかるため、早めに手続きを行うことが大切です。
高額療養費制度
「高額療養費制度」は、医療費の負担を軽減するために、自己負担に上限を設ける制度です。1カ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が後日払い戻されます。吸引分娩などの異常分娩も対象です。
医療費控除
「医療費控除」は、1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超える場合、税金の一部が還付される制度。自分や家族のために支払った医療費が対象で、確定申告を通じて還付を受け取れます。正常分娩の費用も医療費控除の対象となるため、必要に応じて申請しましょう。
吸引分娩の民間保険における注意点

ここまで解説してきたように、吸引分娩は公的保険だけではなく、民間保険の対象にもなりますが、民間保険で備える場合にはいくつか注意点があります。
保険に加入する時期
妊娠が発覚した後では民間の医療保険に入りにくく、加入できるとしても、特定部位(子宮)や異常分娩を対象外とする不担保や保障期間外といった条件付き加入となる可能性があります。そのため、妊娠前に医療保険に加入しておくことで、リスクを避けて安心して出産に備えることができます。
保険金や給付金の支払期限
保険金や給付金の請求は、原則、支払事由が発生した翌日から3年以内に行う必要があります。出産したら早めに手続きを行い、請求期限を過ぎないように注意しましょう。ただし、保険請求期限を過ぎても、必要書類を提出すれば請求できる場合があるため、保険会社に確認することが重要です。
出産に備えて保険の確認を

吸引分娩は異常分娩に該当するため、公的医療保険や民間保険の適用対象となります。また、出産に関してはさまざまな一時金制度があるため、自分がどのような制度を使えるかあらかじめ確認して、出産に備えることが大切です。
ゼクシィ保険ショップでは、妊娠・出産などのライフプランに合わせた保険のアドバイスが受けられます。相談は何度でも無料ですので、保険に悩んでるい方は一度相談してみてはいかがでしょうか?
※掲載の情報は2025年2月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。


RT-00982-2502