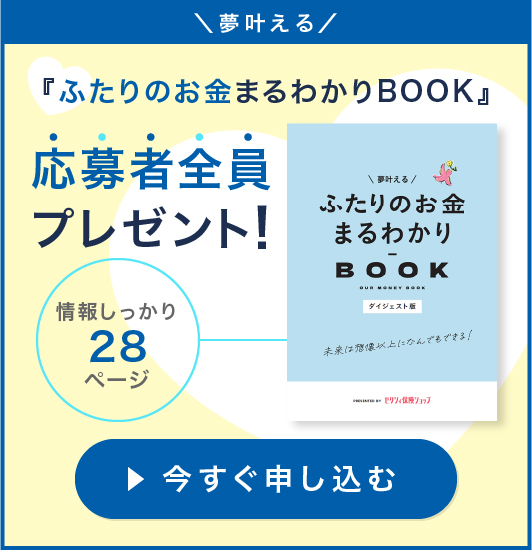妊婦の保険はどうする?リスクや公的制度・かかる費用なども解説

更新日:2025/3/31
妊娠・出産は多額の費用がかかるだけでなく、体調や入院などさまざまなリスクも伴います。事前に準備しておくことで、予期せぬ出費やトラブルに備えることが可能です。この記事では、これから妊娠を考える方や現在妊娠中の方に向け、必要な費用やリスクから、検討すべき保険のことまで詳しく解説します。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる


保険は妊婦になる前の加入がおすすめ

民間の医療保険や生命保険は、妊娠前(できれば妊活前)に加入するのが理想的です。というのも、妊娠中や妊活中は、入院や手術などのリスクが高まり、加入可能な保険が限られる場合があるためです。
また、加入できても保障内容に制限がかかることが多く、選べるプランが狭まります。できるだけ早い段階で保険の加入を検討することで、より幅広い選択肢と充実した保障を得ることができ、安心して妊娠・出産に臨むことができます。
妊娠・出産は基本的に公的医療保険の適用外
通常、病院で使用する「保険証」は国民皆保険制度に基づく公的医療保険のものであり、すべての国民が加入を義務付けられています。この保険が適用されれば、病気やケガに関する医療費の自己負担は原則として3割に抑えられます。
しかし、正常な妊娠や出産は病気ではないとされているため、基本的には公的医療保険の対象外となっています。ただし、自治体による助成制度や、一部医療行為が公的保険の対象となるケースも存在するため、妊娠前に事前確認が必須です。各医療機関での対応状況や助成内容について、詳細を確認し、適切な手続きを行いましょう。
妊娠・出産に必要な費用とは

保険加入検討の前に、妊娠・出産で実際に発生する各種費用を把握しておく必要があります。
妊娠中に必要な費用
妊娠中は計14回ほどの妊婦健診を受けることになります。初回の検診費用は1万円から2万円、以降は5000円前後というのが一般的ですが、医療機関により異なります。血液検査や超音波検査など追加の検査が必要になる場合もあり、その費用は別途発生します。前述の通り、通常の妊娠は公的医療保険の対象外ですが、重度のつわりや妊娠高血圧症候群などで入院した場合は、公的医療保険の適用により自己負担は3割となります。
出産のときに必要な費用
出産時には、入院料、分娩(ぶんべん)料、新生児の管理費、検査や薬剤費など多くの費用が発生しますが、これらの合計はおおよそ40万〜80万円程度が目安となります。正常分娩の場合、こうした費用は基本的に公的医療保険の適用外です。
一方、切迫早産や帝王切開など異常分娩の場合は、その治療費などには公的医療保険が適用されるため、自己負担は3割となります。
妊娠や出産にかかる費用で利用できる公的制度

妊娠・出産費用の一部は、各種公的制度を活用することで負担を軽減できるため、制度の内容を把握しておくことが大切です。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産後に加入している公的医療保険から一時金が支給される制度です。子ども1人につき通常50万円が受け取れます。ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象にならない出産の場合は48万8000円となります。
支給方法には、医療機関に直接支払われる「直接支払制度」と、本人が受け取る「受取代理制度」があります。医療機関が直接支払制度に対応していない場合は、立て替え払いとなるため、出産費用を準備しておく必要があります。制度の詳細や申請方法は、加入している保険の内容をよく確認しましょう。
出産手当金
出産手当金は、会社員の妊婦が出産のために産前産後休暇を取得しており、給与が支払われない場合に、勤務先の健康保険から支給される制度です。支給額は標準報酬日額の3分の2です。これにより、出産による収入減少の補填(ほてん)が期待できます。
傷病手当金
傷病手当金は、会社員・公務員を対象とした給付金で、病気やケガのために会社を休んだ際の収入減少リスクを軽減するための制度です。妊婦の場合、例えば切迫流産やつわりなどで働けなくなった場合に、勤務先の健康保険から支給されます。支給額は標準報酬日額の3分の2で、連続する3日間の無給休業後、休業4日目から支給されます。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1カ月にかかった医療費が自己負担上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。切迫早産や帝王切開など、公的医療保険が適用される医療行為に関わる費用が対象です。医療費が高額になる場合、この制度を活用することで家計の負担を大幅に軽減できます。
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が一定額(原則10万円)を超えた場合、確定申告を行うことで、所得から控除できる制度です。会社員の場合でも、医療費が多額になった場合に確定申告をすると、税金の一部が還付されます。
妊娠・出産で考えておくべきリスク

妊娠・出産に伴うリスクとして、体調の変化や合併症などが考えられ、事前に備える必要があります。
重度のつわり(妊娠悪阻)
重度のつわりは、激しい嘔吐(おうと)や脱水、栄養失調を引き起こし、場合によっては入院が必要になる深刻な症状です。体力の低下や代謝障害により、母体の健康を損なうリスクが高まるため、医療機関での適切な治療と栄養管理が求められます。
切迫早産
切迫早産とは、妊娠22週以降37週未満での出産の危険が高まっている状態を指します。この状態では、長期の入院管理が必要になる場合もあり、母体および胎児へのリスクを早期に察知し、適切な医療措置が求められます。
妊娠高血圧症候群
妊娠高血圧症候群は、妊娠中に高血圧が発症し、母体や胎児に重大な影響を与える疾患です。症状が重い場合は、入院治療が必要となり、早期発見と継続的な管理が不可欠です。定期健診でのチェックが重要です。
妊娠うつ・産後うつ
妊娠中や産後に発症するうつ状態は、女性ホルモンの急激な変化や精神的ストレスが影響し、治療が必要な場合があります。適切なカウンセリングや医療機関での治療を受けることで、母体の心身の健康維持につながります。
帝王切開などの異常分娩
帝王切開は、母体や胎児の状態により、緊急措置として行われる外科手術です。通常の分娩に比べて手術リスクが高く、術後の回復期間も必要となります。帝王切開は近年増加傾向で、2023年では分娩全体のうち帝王切開の割合が29.1%にも上っていることから、こうしたリスクにきちんと備えておく重要性も高いと言えます。
出典:
厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査(確定数)・病院報告の概況」
流産
流産は、妊娠22週未満で胎児が亡くなる事象で、精神的・身体的な負担が大きいです。流産の原因や時期により、入院や手術が必要となる場合もあります。適切な医療ケアと心のサポートが求められます。
妊娠を考えている人が検討するべき保険

妊娠前から検討できる保険には、医療保険、生命保険、学資保険などがあり、将来への備えとして重要です。
医療保険
医療保険は、妊活前や妊娠前から加入することで、妊娠中や出産時のリスクに備える保険です。帝王切開などの異常分娩で入院給付金や手術給付金が受け取れる場合があり、重度のつわりや切迫早産での入院時にも保険金が支払われる可能性が高いです。
妊娠後の加入は条件が厳しくなるため、事前にしっかりと検討することが重要です。
生命保険
生命保険は、自分や配偶者に万一の事態があった際、家族の生活を支えるための資金を確保するためのものです。妊娠・出産を機に新たに加入する方も多く、すでに加入している場合は保障内容の見直しを検討することをおすすめします。
学資保険
学資保険は、生まれてくる子どもの教育資金を準備するための保険です。出生前から加入できるプランもあり、加入時期が早ければ月々の負担が軽減されます。妊娠中に検討を始め、将来の教育費に向けた資金計画を立てることが望ましいです。
迷ったらプロに相談を

妊娠・出産にはさまざまなリスクが伴います。民間保険は、妊娠前からの加入が望ましく、医療保険、生命保険、学資保険など自分たちのライフプランに合わせた選択が重要です。また、基本的に妊娠・出産費用は公的医療保険の適用外ですが、各種公的制度を活用することで負担を軽減できます。
妊娠・出産に備える保険選びや見直しは、自分だけでは判断が難しい場合があります。プロのアドバイザーに相談することで、家計全体を見渡した最適な保険プランが見つかります。
ゼクシィ保険ショップでは保険に関する初歩的な疑問にも丁寧に答えます。「妊娠前にどの保険に入っておけばよいかわからない」「子どもが生まれたら死亡保障の見直しをしたいが、いくらがいいかわからない」などのお悩みがある人は、お気軽にご相談ください。相談は何度でも無料です。
※掲載の情報は2025年3月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。


RT-00987-2503