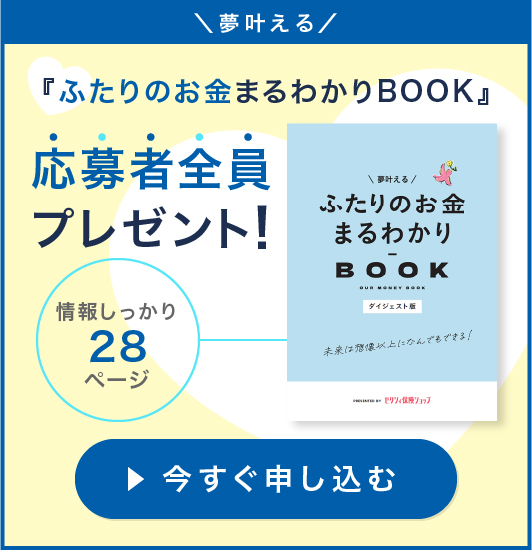学資保険の代わりに教育資金の貯め方はある?方法やメリット・デメリットを解説

更新日:2025/3/31
子どもの教育費を準備する方法として学資保険が広く知られていますが、投資信託や各種保険商品、さらには公的な支援制度など、実はさまざまな選択肢があります。この記事では、学資保険の特徴を整理した上で、学資保険以外の代替手段についても具体的にご紹介します。ぜひ、これからの教育費準備の参考にしてください。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる


学資保険が始まった背景

学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための金融商品です。1971年に郵便局(現・かんぽ生命保険)によって創設され、その後各保険会社が多様なプランを展開しました。
当時は高度経済成長期で教育熱が高まり、大学進学率の上昇に伴ってまとまった教育資金の需要が顕在化していました。これに対応するため、毎月一定額を積み立て、大学進学時などの大きな出費に備えるという仕組みが導入されました。
契約者に万一のことがあっても教育資金が確保される保障があり、長年にわたって日本の教育資金準備の重要な手段として活用されてきました。
そもそも教育資金はいくら必要なのか?

教育資金の必要額は、家庭の経済状況や教育方針、進学先の学校の種類などによって大きく変動します。
国公立学校と私立学校、または留学や特別な教育プログラムに参加する場合など、子ども一人一人の環境に応じた費用が発生するため、一概に金額を決めることは困難です。そのため、家庭内で教育に対する考え方を話し合い、具体的な目標や将来像を共有することが重要です。こうすることで、どの段階でどの程度の支出が必要かを明確にでき、より現実的な貯蓄計画が立てやすくなります。
幼稚園から高校までにかかる費用
幼稚園から高校までの15年間の教育費総額は、進路選択で大きく変わってきます。
文部科学省の調査によると、最も費用が抑えられる「全公立コース」は約596万円ですが、私立校を加えると費用は段階的に増加。例えば「高校のみ私立」だと725万円、「幼稚園と高校が私立」で776万円となります。「全私立」だと約1976万円となり、全公立の3.3倍に達します。
特に私立小学校の費用は公立の約5倍と突出して高く、小学校の選択によって教育費の総費用が大幅に変わることが分かります。
文部科学省「調査結果の概要‐令和5年度子供の学習費調査」
大学にかかる費用
文部科学省の「令和6年度学校基本調査」によれば、2024年の大学進学率は59.1%と約6割に上ります。
大学費用は主に、入学時の入学料と毎年の授業料で構成されます。国公立大学と私立大学では費用に差があり、2023年のデータでは私立大学の場合、入学料が約24万5951円、授業料が年間約93万943円。国立大学は入学料約28万2000円、授業料年約53万5800円、公立大学は入学料約39万1305円、授業料年約53万6363円となっています。さらに、生活費や教材費、就職活動に伴う出費なども必要となるため、総額はかなりの金額になることが多く、早期からの資金準備が不可欠です。
※出典:
文部科学省「令和6年度学校基本調査 確定値について」
文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」
学資保険のメリット
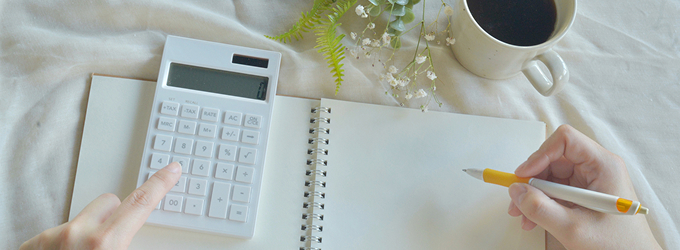
学資保険は、貯蓄性と保障の両立を備え、教育資金を確実に準備したい親御さんの強い味方となる保険です。以下、その主なメリットを詳しく見ていきます。
教育費の計画を立てやすい
学資保険は、契約時に払込期間や受け取り時期が明確に定められているため、計画的に教育資金を準備できます。
毎月一定額の支払いにより家計管理がしやすく、大学進学時など大きな出費にも備えられる点が魅力です。さらに、貯蓄が苦手な人でも強制的に積み立てが行えるため、確実な資金確保が可能です。
親に万が一のことがあった際に保険料の支払いが免除される
学資保険には、契約者に万一の事態が発生した場合、以降の保険料が免除される特約が付いていることが多くなっています。これにより、親が亡くなった場合でも子どもの進学資金が予定通り給付されるため、安心感が得られます。
生命保険料控除の対象になる
学資保険の保険料は、所得税や住民税の計算において生命保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告の際に控除を受けることで、課税所得が減少し、結果として税負担の軽減につながります。
学資保険のデメリット

学資保険にはいくつかの注意点も存在します。特に気を付けるべきデメリットも合わせてチェックしておきましょう。
途中解約により元本割れのリスクがある
学資保険は長期契約のため、途中で解約をすると支払った掛け金以上の返戻金が受け取れない場合が多く、元本割れのリスクがあります。将来の教育費に備えるためにも、契約期間中は基本的に解約を避け、計画通りの積み立てを続けることが重要です。
学資保険が向いている人
学資保険は受取金額があらかじめ決まっており、元本割れのリスクが低いこと、さらに契約者が万一の場合に保険料が免除されるなどの保障がある点から、リスクを極力避けて計画的に教育資金を準備したい方に適しています。
投資による価格変動リスクを回避し、確実な資金形成を目指す家庭にとって、安心感と計画性を兼ね備えた最適な選択肢と言えます。
学資保険の代わりに活用できる保険

学資保険以外にも、さまざまな保険商品が教育資金の準備に活用できる手段として存在します。自分のライフプランに合ったものを選ぶためには、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
低解約返戻金型終身保険
低解約返戻金型終身保険は、一生涯の死亡保障を備えつつ、教育資金準備に活用できる保険です。加入時に保険料の払込期間を設定し、大学進学時など必要なタイミングで解約返戻金を受け取る仕組みになっています。
払込期間中は解約返戻金が低く設定されていますが、払い終えた後は返戻率が急上昇するため、進学時期に合わせて解約すれば効率的な資金形成が可能です。ただし、払込期間中の解約は元本割れリスクが高いため、家計の安定性を確認した上で加入計画を立てることが重要です。
外貨建て終身保険
外貨建て終身保険は、外貨で保険料を払い込み、解約返戻金や死亡保険金も外貨で受け取る商品です。円建て保険より金利が高く、為替差益も期待できる点が特徴です。例えば円安時に解約すれば、外貨ベースの返戻金が円換算で増加し、効率的な資金形成が可能です。
ただし、為替変動のリスクが付きまとい、保険料に対して受け取る金額が目減りする可能性もあります。学資保険と比べると高い運用益を狙えますが、リスクとリターンのバランスをしっかり考慮することが前提となります。
変額保険
変額保険は、保険料を株式や投資信託で運用し、実績に応じて解約返戻金や満期金が変動する生命保険です。
死亡保険金は最低保証額が設定され、万一の場合でも基準金額を下回りませんが、解約時には運用成績次第で元本割れのリスクがあります。投資リスクを許容しつつ、インフレ対策や資産形成を兼ねた保障を求める人向けです。
学資保険の代わりに資金を貯める方法

学資保険や上で紹介した保険以外にも、投資や支援制度を活用して効率的に教育資金を準備する方法が存在します。
投資信託
投資信託は、専門家が資産を分散投資し、その運用成果を投資家に還元する金融商品です。少額から投資を始めることができ、初心者でも取り組みやすい点が魅力です。市場環境や運用状況に応じてリターンが変動するリスクはありますが、柔軟に現金化できるメリットがあり、急な出費にも対応可能です。
投資信託は、運用実績が良好な場合、通常の貯蓄よりも大きなリターンが期待できる商品です。そのため、ある程度のリスクを取っても、学資保険以上のリターンを狙いたいという人には魅力的な選択肢となります。
また掛け金や運用期間に縛られることなく、自由に現金化でき、教育費以外の目的でも利用できるため、資金計画に柔軟を持たせたいという人にもおすすめです。
インフレのリスクがある
長期にわたる学資保険は契約時の金額で受け取るため、将来的な物価上昇の影響を受けやすいです。インフレが進むと、現在の金額で購入した商品やサービスの価値が、将来に下がってしまうリスクがあります。
NISA
NISAは、個人で投資を後押しする国の投資制度。株式や投資信託の配当金・分配金や売却益が非課税となるのが大きなメリットです。少額からの積み立てが可能で家計の状況に合わせて投資金額を調整でき、必要に応じて現金化できるなど柔軟性もあります。コツコツと長期的な積立投資が行えるため、教育資金の形成にも適しています。
手当や支援制度

家庭の経済状況をサポートする各種手当や公的支援制度も、教育資金の準備に大いに役立ちます。これらを賢く利用することで、家計負担を軽減しながら必要な資金を確保することができます。
児童手当
児童手当は、子どもが生まれた家庭に対して支給される手当。年齢や子どもの人数によって支給額が変動します。2024年10月以降、支給対象が高校生まで拡充され、所得制限も緩和されたことから、より多くの家庭で利用できるようになりました。
定期的に受け取れる手当は、毎月の家計の中で教育資金として積み立てることも可能で、長期的な資金形成の一助となります。
就学援助制度
就学援助制度は、経済的な理由で学校進学が困難な家庭に対し、小中学校関連の費用を援助する制度です。援助対象には学用品費、給食費、卒業アルバム費、入学準備金などが含まれており、地域ごとに支援内容や申請方法が異なります。
高等学校等就学支援金制度
高等学校等就学支援金制度は、高校の学費(授業料)軽減を目的として設けられた支援金制度です。所得要件は年収約910万円未満の家庭が対象で、申請は学校から配布される書類とマイナンバーカードの控えを用いて行われます。
奨学金制度
奨学金制度は、日本学生支援機構などが運営する制度で、学生の経済的負担を軽減するための支援策です。返済が必要な「貸与型」と、返済不要の「給付型」があり、いずれも学力や所得などの要件が設定されています。
国の教育ローン(教育一般貸付)
教育ローンは、日本政策金融公庫が運営する国の制度で、世帯年収が一定額を下回る世帯であれば、教育費を賄うための資金が借りられます。最大350万円まで一括で借り入れ可能、返済期間は最長18年です。固定金利は年2.4%が基本ですが、条件により金利優遇も受けられます。
将来設計を見据えて選択を

計画的に積み立てつつ、万一の際の保障も確保できる学資保険は、子どもの教育資金に備えるのに適しています。ただし学資保険以外にも、他の保険や投資信託、NISAなど、教育資金を貯める方法は多岐にわたります。各制度の特徴を理解し、家庭の状況や将来設計に合わせた方法を選択することが大切です。
ゼクシィ保険ショップでは、各家庭のライフプランに合わせた保険のアドバイスが可能です。「学資保険は必要?」「どんな保険に入ったらいいの?」など保険に関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。
※掲載の情報は2025年3月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。


RT-00986-2503