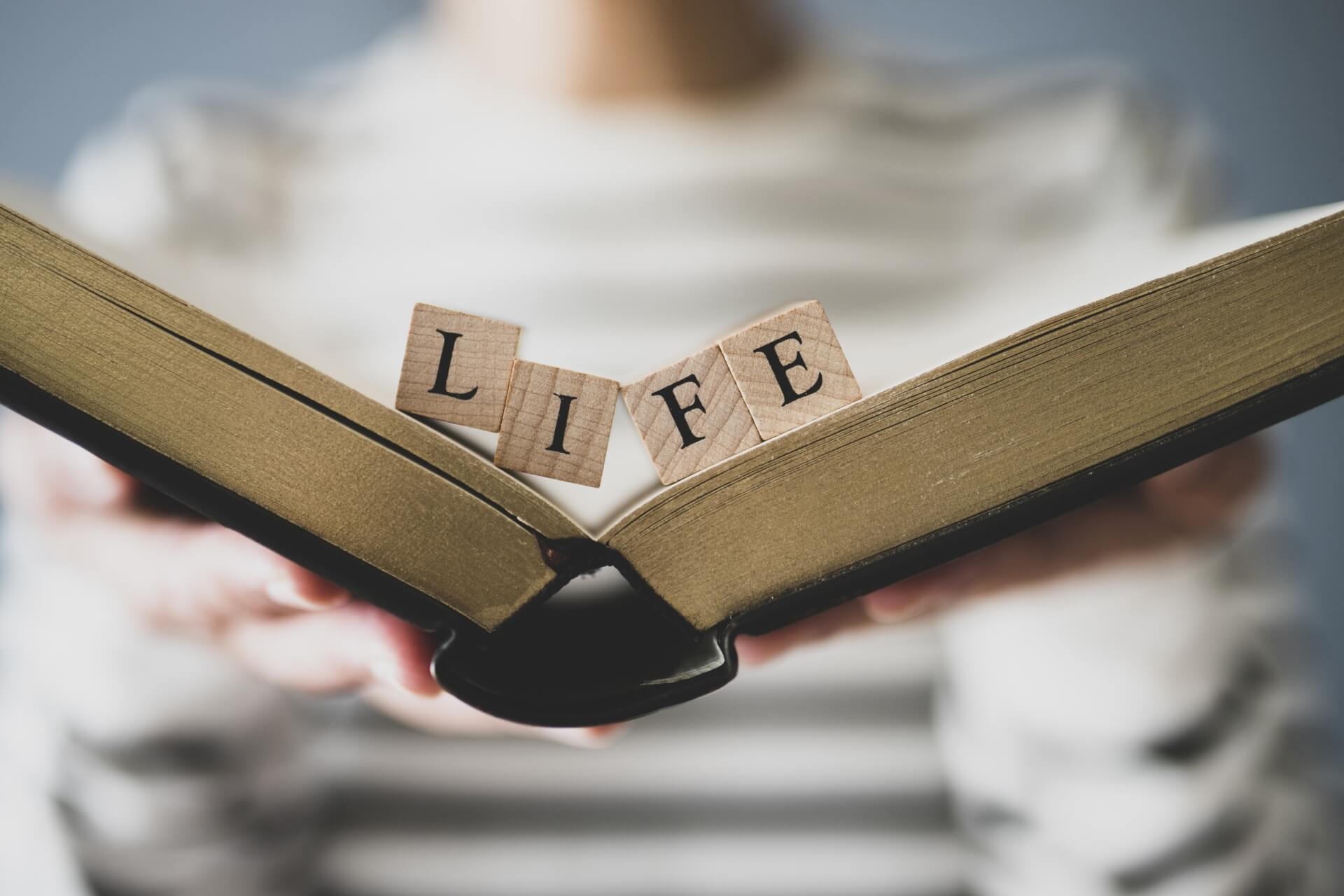保険の仕組みとは?生命保険・損害保険の仕組みについて解説

更新日:2022/6/22
「万が一のために保険に加入した方がいいのかな?」と思いながらも、難しくて何を選べばよいかわからないと感じている人も多いでしょう。この記事では、これから保険への加入を検討している人に向けて、保険の種類や仕組みについて解説していきます。皆さんの保険選びにぜひ役立ててください。
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
保険とは?

保険とは、将来起こる可能性のあるさまざまな“リスク”に備える制度です。病気・けが・死亡・事故・自然災害など日常生活で起こり得るリスクは、事前に予測することもできないため、個人の力だけでそれら全てに対処するのは困難でしょう。
そこで、同じように不安を感じている人々で助け合う、“相互扶助”のシステムが保険です。みんなでお金(保険料)を出し合い、万が一の事態が起きたら、その集めたお金の中から保険金を受け取ることができます。
日本の保険の歴史
そもそも保険はいつから日本に存在するのでしょうか。
実は、日本に保険という考え方を持ち込んだのは、近代教育の父といわれ、慶応義塾大学の創始者でもある福澤諭吉です。明治時代が幕開けする頃、著書『西洋旅案内』の中で、ヨーロッパの「近代的保険制度」を紹介しました。そして、1881年に日本最古の保険会社が、福澤諭吉の門下生である阿部泰蔵によって設立されました。その後、日本にさまざまな保険会社が設立され、徐々に一般の人々にも普及していきました。
保険が必要な理由

保険が必要な理由は「日常生活におけるリスクへの備え」です。保険の大きな特徴は、保険期間中であれば、万が一の事態が起こったときに、確実に保険金を受け取れることです。同じく経済的なリスクに備える目的なら、貯蓄でもよいのではと思う人もいるかもしれませんが、貯蓄では貯めた金額分しか利用することができません。そのため、もし貯蓄を始めてすぐ病気になった場合には、完全に対応するのは難しくなるでしょう。よって、経済的なリスクに少しでも万全に備えるためには、保険が必要だと言えるでしょう。
保険の種類
現代では新しい保険商品が次々と登場しており、ひと言で保険と言っても、その種類や組み合わせはさまざまです。そのため、「保険って複雑で選ぶのが難しい」というイメージを抱いている方もいるかもしれません。しかし、見方を変えれば、選択肢が多い分、自分に合った保険を見つけやすいということです。
自分にぴったりの保険を見つけるためには、保険の内容をしっかりと理解することがとても大切です。まずは保険をきちんと知るために「リスクに備える3つの保障」について理解し、さらに「保険の分類」について確認していきましょう。
リスクに備える3つの保障

リスクに備える保障の考え方として、以下の3つを押さえておきましょう。
1.公的保障(国など)
公的保障とは、国・地方自治体が国民の健康で文化的な生活を守ることを目的として提供する公的な保障制度です。公的年金・公的医療保険、介護保険などがこれに当てはまります。
日本においては、公的年金と公的医療保険、40歳以上は介護保険について全ての国民に加入が義務付けられています。なぜならば、病気やけがなどの健康に関するリスク、老後の生活費や介護費が発生した場合に、“セーフティーネット”の役割を果たすものだからです。
2.企業保障(会社)
企業保障とは、企業が経済活動をする上でのリスクに備えるために加入する保険のことです。
企業保障は、国が運営する公的年金と連動した厚生年金、国民健康保険とは別に独自に運営する健康保険、国が運営する介護保険の3つがあります。これに加えて、会社に勤務する際に起こるリスクに備えて「労災保険」と「雇用保険」があり、会社員であれば誰もが加入することになっています。
3.私的保障(個人)
公的保障と企業保障では足りない部分をカバーするために、自分で選択し自力で備える保険を私的保障と言います。
私的保障は、「貯蓄」「保険・共済」の2つに分類することができます。2種類の中では、貯蓄が唯一資金の出し入れが自由に行えるため、気軽に始められる方法でしょう。一方で、リスクに備えられる十分な貯蓄が自力ではつくれない場合は、保険や共済に加入することでカバーできます。
保険の分類
保険の分類は、「生命保険」と「損害保険」の2つに分かれます。この2つは、保険を備える目的・対象が異なっています。簡単に言えば、生命保険は、基本的に人の生死やけが・病気、その他の人的リスクに対して備えるもので、損害保険は物自体の破損や物による破損に対して備えるものです。これら2つについて、詳しく解説していきます。
生命保険
生命保険とは、自分とその家族の生活を守るための保険です。いくつもの種類がありますが、代表的なものとしては、病気やけがなどに備える「医療保険」。特にがんの治療だけに備える「がん保険」。契約者が亡くなったときに遺族に支払われる「死亡保険」(生命保険)。働けなくなったときに備える「就業不能保険」、介護時に備える「介護保険」などがあります。それぞれ、契約に応じて、給付金や保険金が受け取れます。
損害保険
損害保険は物が破損したときに“補償”される保険です。“補償”という漢字を用いるのは、損害保険は、基本的には実際に発生した損害額を補償する「実損払い方式」が中心であるからです。
損害保険の種類としては、「自動車保険」「火災保険・地震保険」などが挙げられます。契約時には上限金額を設定しますが、基本的には実損を全て補償してくれます。一方で、定額で保険金がもらえる生命保険とは違い、補う以上の金額が受け取れることはありません。
保険の仕組み

生命保険と損害保険の仕組みや保険料の計算方法などを詳しく解説します。
生命保険の仕組み
生命保険では、多くの加入者が保険料を公平に負担し、共同の大きな資産をつくります。そして、その資産を資金源として、万が一のことが起こった人に保険金や給付金を拠出するという仕組みになっています。つまり、「自分の万一の備えに」と加入する保険ですが、全体として見ると一人一人が互いに支え合う、「相互扶助」の仕組みによって成り立っています。集めた資産は保険会社が管理しており、もしものときのお金は保険会社から支給されます。
保険料の計算方法
生命保険の保険料はまず、「収支相等の原則」に沿って計算されます。これは、集めた保険料(収入)と支払った保険金(支出)が等しくなるように保険料を設定するという考え方です。具体的には、「保険金×死亡者数=保険料×契約者数」という計算式が成り立つように設定されます。
また、保険金をもらうリスクは人によって異なります。そのため、保険会社が引き受けるリスクの高低に保険料を比例させた方が、より公平な負担となります。これを「給付反対給付均等の原則」といい、この2つの原則によって保険料を算出しています。
損害保険の仕組み
損害保険の仕組みも、生命保険と大きな違いはありません。多くの加入者が保険料を公平に負担してつくった共同の資産から、事故や災害などで損害を被った加入者に対し補償するという仕組みになっています。生命保険と同様、不安を感じている加入者同士が互いに助け合う相互扶助の精神から生まれた仕組みです。
保険料の計算方法
損害保険の保険料は、純保険料と付加保険料の2つで構成されています。純保険料は、保険会社が支払う保険金の原資になる部分です。基本的には、生命保険の保険料と同様で、「収支相等の原則」と「給付反対給付均等の原則」を基に算定されます。
一方、付加保険料は、事業運営に必要な費用を賄うための費用になる部分です。そのため、契約者の利益、保険会社の担保力、契約者間の公平などの観点から、各保険会社が独自に算定しています。
【まとめ】仕組みを理解して最適な保険選びを
このように、「種類が多すぎて複雑だ……」と敬遠しがちな保険ですが、仕組みがわかれば、自分の生活スタイルに合わせて“カスタマイズ”ができる商品とわかります。
しかし、保険選びは、検討すべき要素が多々あり、自分に最適な保険を選ぶのは至難の業。
自分で選ぶのが不安だという場合はプロに相談することをお勧めします。
ゼクシィ保険ショップでは、保険だけでなく、家計やライフプランの提案もできます。保険に関して知識がないけれど、加入を検討したいという人もぜひ相談してください。
※掲載の情報は2022年6月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00500-2206