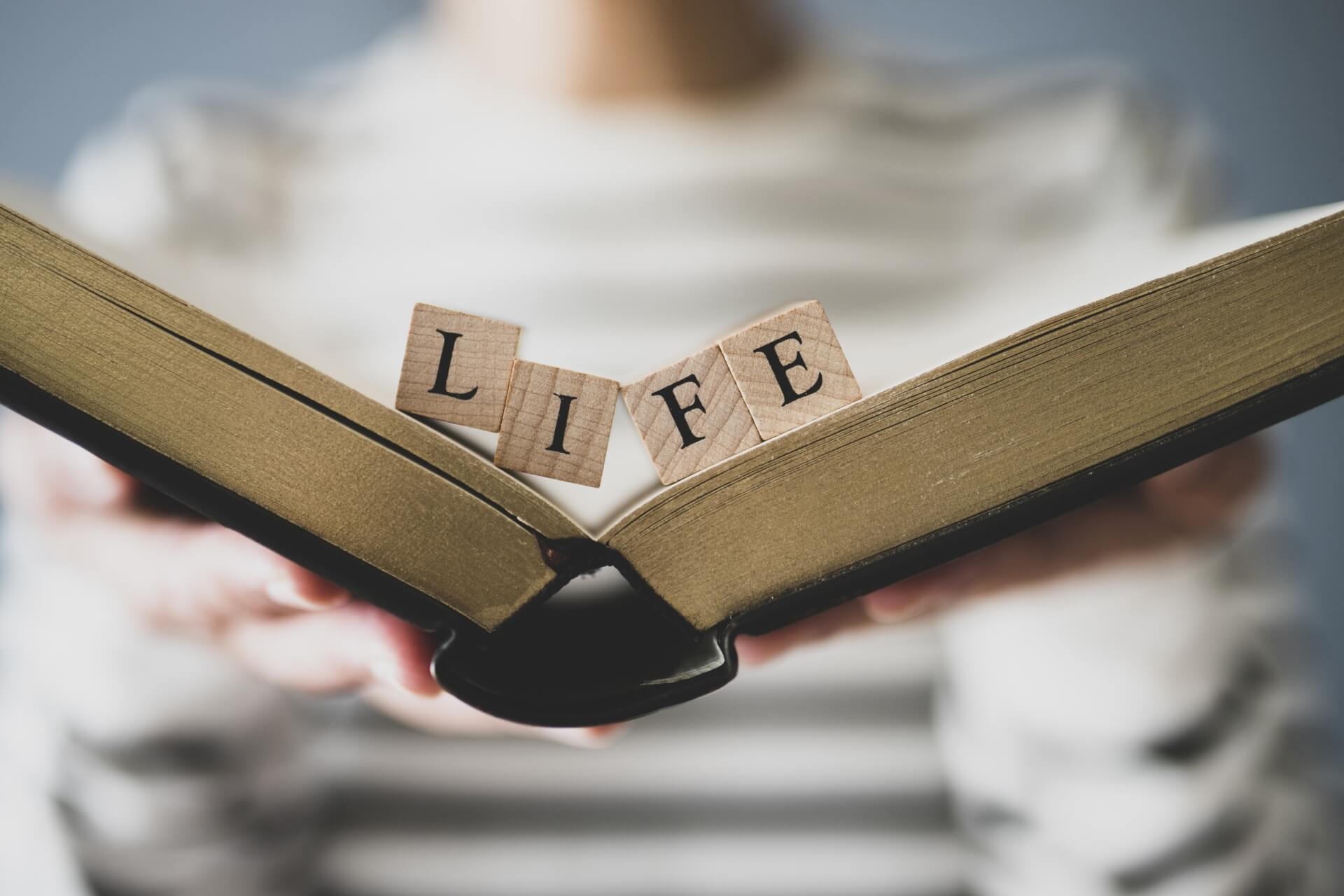生命保険の配当金について

更新日:2020/10/21
目次(読みたいところまで飛べます) 閉じる
配当金の仕組み
多くの人が保険料を払い込み、助け合うというのが生命保険の基本的な仕組み。保険料は、将来の見込みを基に保険会社が決定し、加入者が負担し合います。配当金は、見込みと実際の差により生じるいわば「保険料のお釣り」のようなもので、毎年必ず受け取れるわけではありません。
配当金はどうやって生まれる?
生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配がない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。 では配当金とはどのように生じるのでしょうか?
まず原則として、保険料は、「契約者全員が払い込む保険料の総額・運用収支」と「受取人が受け取る保険金などの総額・生命保険事業の運営経費」が等しくなるよう決められています。これは「収支相等の原則」といいますが、この原則に従った上で、保険料は「予定率」に基づいて算出されます。
この予定率は、予定死亡率(死亡者数はどのくらいか)、予定利率(資産運用をして得られる収益はどのくらいか)、予定事業比率(生命保険会社の経費はどのくらいか)の3つを基に決められます。とはいえこれらはあくまで「予定」であって、契約時に見込まれた「予定率」と「実際の率」に差が生じることがあります。
そして有配当の保険で、保険料を決める予定率と実際の率との差による「余り」があれば、配当金が契約者に返されます。運用環境の悪化などにより、余りがないと、配当金はゼロになります。配当金があるかないか、またその額がいくらかは、保険種類など契約内容によって異なります。
有配当の保険の種類について
有配当の保険には、以下の2種類があります。
●3利源配当タイプ
3つの「予定率」を基に立てた予測と、実際の率との差によって「余り」があった場合に、毎年配当金を受け取れる生命保険。
●利差配当タイプ
「予測利率」だけを基に立てた予測と、実際の率との差によって「余り」があった場合に、配当金を受け取れる生命保険。
配当金の受け取り方法
配当金の受け取り方法は主に2種類で、加入時に決めます(生命保険の種類によっては、受け取り方法が決まっていて選択できない場合もあります)。
一つは「積み立て」という方法。配当金をすぐに受け取らず、生命保険会社の定める利率で積み立てておく方法です。保険会社で積み立てることで、配当金に一定の利息が付くのがメリット。最近では、積み立ての途中でも、一部の金額を引き出すことができる商品が増えてきています。
もう一つは「買い増し」といって、配当金を保険料として生命保険を買い増しし、保障額を増やしていく方法です。メリットとしては、保険金が増え、保障が手厚くなることが挙げられます。主に終身保険や養老保険など貯蓄性のある保険の買い増しに用いられます。
積み立てがいいのか、買い増しがいいのかは、自分の生活の状況や将来のライフプランによって決めるといいでしょう。
有配当=得というわけではない
言うまでもなく、有配当の保険のメリットは一定の剰余金が発生した場合に配当金がもらえるということです。配当金は景気や運用実績に左右されるため、とりわけ好景気でインフレ傾向にあるときなどは、配当金が増えて得をする可能性が高くなります。
ただし、有配当の保険は無配当の保険に比べて保険料が割高になります。また、配当金は必ず受け取れることが確約されたものではなく、運用実績によっては出ないこともあります。低金利が続き、デフレ傾向にある今日のような状況では、ほとんど配当金を期待できないというのが実状です。
こういったことから、保険の検討をする際には配当金を目的にするのではなく、保障内容が自分のニーズに沿っているかどうかを重視することが大切です。
※掲載の情報は2020年9月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。
RT-00361-2010